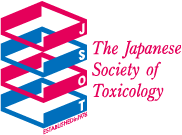学会概要/理事長挨拶
第12代理事長挨拶

毒性学は,あらゆる経路で身体に入り込む種々の外来性物質(xenobiotics)が引き起こす生体反応を動物実験等の利用可能な手段を用いて明らかにし,その情報から被害を予測して未然に防ぐ学問であり,最終目標を「人の安全」とする,純粋科学,応用科学及び社会科学の複合体です。
これを研究する日本毒性学会は,各方面からの要請によりその守備範囲を充実させ,成長してきた歴史を有しております。
私が部長を務める国立医薬品食品衛生研究所・安全性生物試験研究センター・毒性部は,サリドマイド禍を契機に同研究所内に設置されました。「薬効」が睡眠から抗がんへ変遷してきたこの物質は,毒性学を象徴的に示していると考えられます。すなわち,化学物質は生体内に複数の標的を持ち,複数の生体作用を発揮すること,そして,「薬効」は,その内の『その時の患者に都合が良い』生体作用であり,『その時には都合が悪い』生体作用は「副作用」或いは「毒性」として認識される,と言うことを示しています。
新しい生体内標的は関連する純粋科学の成果として次々に見つかり,変遷する薬効や毒性は応用科学で検討されています。1981 年のノーベル医学生理学賞(Hubel and Wiesel)は網膜からの神経シグナルの変調のみで発達期の大脳視覚野の構造と機能の異常が誘発される事を示しましたが,これは所謂「シグナル毒性」の典型例であると解釈されます。先の年会でサリン禍を取り上げた際,慢性・遅発性の高次神経機能障害が問題であることが臨床の先生方からの報告で明らかになり,その中にはシグナル毒性を考慮せざるを得ない事例も含まれておりました。この様に,新たな標的と生体影響の分析には,関連基礎科学に加え日本中毒学会等の臨床科学分野との交流が重要であると考えます。
さて,2011 年3 月の震災,それに続く放射能禍は毒性学に新たな課題を与えました。その一つは毒性学と放射線医学・影響学の摺り合せの必要性です。化学物質のリスク評価・管理を行う際に,科学的知見に不足や不確実性があった場合には適切な仮説を設定してきた事に比べて,今般の放射線に関するリスク管理が仮説を採用せずリスク評価を介さずに行われた事例によって明らかとなった諸問題が存在します。この背景には,基礎科学及び応用科学のレベルで,放射線と化学物質の生体影響の共通性(相互作用も含め)と特異性の検討が体系的に進んでいないことが考えられます。ここで,付随的に表面化するのが,国家レベルで危惧する集団リスクと個々人が感じるリスクの差の問題です。ある特定の癌により200 人に1 人死亡が増えるかもしれないと言われても,199 人の個人には全く意識されないでしょう。これは「ゼロリスク」精神の問題と絡み,安全安心問題の根幹の一つとなり,今後の毒性学の社会科学的課題となります。
毒性学は守備範囲が広く,また,更に拡大すべき社会的要請があります。遠藤仁先生の記された「学会の使命・概要」(http://www.jsot.gr.jp/about/index.html)に有る通り,「学」,「産」,そして「官」が合流し成長してきた本学会は,現在「医」や「社」との連携を進める必然性を有する立場に置かれています。「医」には救急医療や慢性・遅発性後遺症の中毒学(医薬品副作用を含む),産業医学(アスベストなどの労働暴露+新規物質),或いは医薬品の治験(小児治験問題などを含む),「社」には繰り返される「安全と安心の違い」に関するリスクコミュニケーションの問題などがあります。
この度,日本毒性学会の理事長という大役を仰せつかり,2012 年1月からの2 年間を務めさせて頂くことになりました。本学会は,学会員数が2,600 人を超え増加傾向にあり,国際的にも,米国SOT に次ぐ会員数を有する毒性学会に成長しております。今までに培った学会活動はそれらを堅持・増強し,その上に新たな活動を展開すべく尽力する所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2012年1月 菅野 純