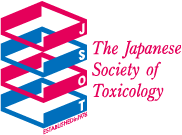学会概要/理事長挨拶
第13代理事長挨拶

この度、日本毒性学会の理事長という大役を仰せつかり、2014年1月からの2年間余を務めさせて頂くことになりました。本学会は、学会員数が2,600人を超え、国際的にも米国SOTに次ぐ会員数を有する毒性学会としてさらに成長の途にあります。諸先輩方の大いなるご貢献により築かれた伝統を堅持すると共に、その上に新たな活動を展開すべく理事・監事の先生方と共に尽力する所存でございます。どうぞよろしくご指導、ご鞭撻の程お願い申し上げます。
さて、我々を取り巻く環境には、天然物質に加え極めて多種の合成化学物質が存在しています。先達のご指摘の通り、毒性学はこれら天然物質や合成化学物質の生体への影響を科学的手法を用いて明らかにし、その情報を基にヒトを含む動物、植物さらには生態系への被害を予測するとともに未然に防ぐことを目的としており、幅広い分野での研究が不可欠な学際的学問です。したがって、毒性学を研究する本学会は、産官学の研究者が結集し成長してきた歴史を有しています。官学ご出身の歴代の理事長に続き、産出身として初めて私が理事長を拝命した背景にはこのような歴史があるものと認識しております。
中世の医師パラケルススは「すべての物質は毒であり、毒でないものは有り得ず、まさに用量が毒と薬を区別する。」と述べています。化学物質の作用はいくつかの様式として発現し、例えば医薬品の場合には「患者に都合の良い生体作用」が薬効として活用されますが、「都合の悪い生体作用」は有害作用、副作用、あるいは毒性として認識されます。有害作用には腫瘍誘発性、肝障害・腎障害等種々の組織障害、あるいは循環障害等の機能障害が含まれます。環境汚染物質の場合には疫学調査やケーススタディによりヒトでの曝露レベル、有害事象の発生頻度を調べヒトでのリスクを評価します。有害物質の場合にはヒトへの曝露を低減するために環境中の物質量を削減する施策が重要となります。
「ヒトの安全」を保証するためには動物実験等によりそれぞれの物質について有害作用の有無・特徴を把握し、有害作用の指標となる検査方法を見出すことが必要です。そのツールとして近年の研究の進展が目覚しいものにバイオマーカーがあります。適切なバイオマーカーは、その有害作用の検出に特異的かつ高感度であることが求められ、従来の臨床検査項目の他、遺伝子、たんぱく質や生体内代謝物も活用されるようになっています。国内では2002年より10年間、国立医薬品食品衛生研究所および独立行政法人医薬基盤研究所を中心とした産官学共同トキシコゲノミクスプロジェクトで150化合物について遺伝子発現の変動解析が実施されました。また、翻訳に関わらない短鎖RNA(miRNA)が細胞や生体の機能や分化の制御に重要な役割を果たしていることが明らかとなりました。細胞のエネルギー代謝や細胞周期等を評価できる複数のバイオマーカーを障害の診断や予測に用いる可能性も示唆されています。今後、これらの中から実用可能なバイオマーカーが確立されることが期待されます。
一方、バイオ医薬品の一つとして、免疫システムの主役である抗体を主成分とした医薬品(抗体医薬品)として1986年にマウスモノクロナール抗体が米国で認可されてから、副作用の少ないヒト抗体に近づけたキメラ抗体、ヒト型化抗体が医薬品として開発され市販されています。その他のバイオ医薬として遺伝子治療薬、核酸医薬品の開発が行われており、再生医療としてヒトiPS細胞を用いた臨床試験開始が2013年に話題となりました。抗体医薬品開発には日米欧でそれぞれ指針が発出されており実験動物等を用いた標準的な安全性評価法が確立していますが、遺伝子治療薬、核酸医薬品、再生医療ではケースバイケースでの対応となっています。今後、それぞれのバイオ医薬品に関して臨床試験を含めた安全性評価法の標準化と確立に産官学のさらなる協力が重要となります。
以上のように、毒性学には守備範囲を更に拡大すべき社会的要請があります。遠藤仁先生の記された「学会の使命・概要」に有る通り、「学」、「産」、そして「官」が合流し成長してきた本学会は、現在「医学」や「社会」との連携を進める必然性を有する立場に置かれています。歴代の理事長、そして菅野前理事長が示されてきた方向性を過たず、これを再度十分に認識の上、日々拡大する学術的知見を横断的に統合し、継続的に社会生活の質向上につなげていく事を使命とし、日本毒性学会の活動をさらに進めたいと考えております。
2014年1月 眞鍋 淳