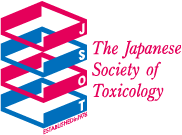学会概要/日本毒性学会の歩み
1.はじめに
古代に暗殺や戦争の目的で使われた動物毒、植物抽出物は、中世を経て20世紀になりトキシコロジーToxicologyの誕生のきっかけとなった。トキシコロジーは100年以上の歴史を持つ薬理学や病理学に比べてようやく50年を過ぎたばかりの新しい学問である。しかし、基礎および臨床医学、薬学における境界領域の学問としてその重要性は極めて大きい。医薬品の副作用や食品添加物の毒性を多角的に究める学問である。また、トキシコロジーは象牙の塔に留まることなく社会と広い接点を持つことも特徴の一つである。日本毒性学会では、毎年市民公開セミナーを開催して、毒性学の啓蒙に尽くしている。また、新薬の開発において、安全性を正しく評価し、リスクを最小化することは製薬企業研究者の重要な責務であり、トキシコロジーがその基盤となっている。
2.トキシコロジーの幕開け
トキシコロジーが学問として認知されたのは1960年代初頭である。その頃のトキシコロジーは、薬理学、病理学、生化学などの研究者が集まったいわば「ヘテロ集団」だった。その最初の専門家集団は、1961年3月4日に9名の発起人により設立された米国トキシコロジー学会(Society of Toxicology)である。設立当初は僅か500名の会員であったが、約60年を経た現在、7800名余の会員にまで成長し世界で最大のトキシコロジー学会となった。一方、欧州では、1962年9月20日に欧州6カ国から19社の大手製薬企業関係者26名が集まり、欧州における毒性研究の学術グループの必要性が検討された。その結果、European Society for the Study of Drug Toxicity(ESSDT)が設立された。当時ドイツで起きたサリドマイドの悲劇がESSDT設立の引き金になったといわれている。ESSDTは10年後にEuropean Society of Toxicology(EST)と名称を改め、その後現在のFederation of European Toxicologists & European Societies of Toxicology (EUROTOX)となった。
3.日本毒科学会の設立
我が国における初の毒性研究者集団は、1973年11月に設立された「毒性研究会」である。会員の多くは獣医系大学および製薬企業の研究者であった。その後、1975年には医学、薬学系の研究者が中心となり「日本毒作用研究会」が設立された。1976年には同研究会の機関誌としてThe Journal of Toxicological Sciencesが創刊された。同年、毒性研究会は発展的に解散し、日本毒作用研究会と合流した。国際的には、1980年、日本毒作用研究会はInternational Union of Toxicology (IUTOX)に加盟した。1981年6月に日本毒作用研究会は発展的に解散し、「日本毒科学会The Japanese Society of Toxicological Sciences」が設立された。
初代役員(1981-1984)(敬称略、所属は就任時)
理事長
田邉恒義(北海道大学医学部)
理事(順不同)
酒井文徳(東京大学医学部)
村野 匡(和歌山県立医科大学)
石川榮世(東京慈恵会医科大学医学部)
大森義仁(国立衛生試験所)
織田敏次(東京大学医学部)
館 正知(岐阜大学医学部)
柳谷岩雄(大阪府立大学農学部)
山野俊雄(大阪大学医学部)
吉村英敏(九州大学薬学部)
柳田知司(実験動物中央研究所)
塚田裕三(慶応義塾大学医学部)
堀口俊一(大阪府立大学農学部)
福田英臣(東京大学薬学部)
粕谷 豊(東京大学薬学部)
池田正之(東北大学医学部)
白須泰彦((財)残留農薬研究所)
今道友則(日本獣医畜産大学)
北川晴雄(千葉大学薬学部)
加藤隆一(慶応義塾大学医学部)
吐山豊秋(東京農工大学農学部)
監事
藤原公策(東京大学農学部)
藤村 一(京都薬科大学)
河合清之(産業医学総合研究所)
その後、同学会は今日まで名称を2回変更したが、現在、役員は2年毎に改選されている。
歴代理事長(敬称略、所属は就任時)
田邉恒義(1981-1984)(北海道大学医学部)
酒井文徳(1984-1987、1987-1990)(東京大学医学部)
和田 攻(1990-1993)(東京大学医学部)
福田英臣(1993-1996)(東京大学薬学部)
黒川雄二(1996-1999)(国立医薬品食品衛生研究所)
唐木英明(1999-2001)(東京大学農学部)
遠藤 仁(2002-2004)(杏林大学医学部)
長尾 拓(2005-2006.6)(東京大学薬学部)
土井邦雄(2006.7-2007)(東京大学農学部)
山添 康(2008-2009)(東北大学薬学部)
吉田武美(2010-2011)(昭和大学薬学部)
菅野 純(2012-2013)(国立医薬品食品衛生研究所)
眞鍋 淳(2014-2015)(第一三共株式会社)(法人化に伴う事業年度の変更に伴う2年半の任期)
永沼 章(2016-2017)(東北大学薬学部)
熊谷嘉人(2018-2019)(筑波大学医学医療系)
菅野 純(2020-2021)(国立医薬品食品衛生研究所)
務台 衛(2022-2023)(LSIM安全科学研究所)
広瀬明彦(2024-2025)(一般財団法人化学物質評価研究機構)
日本毒性学会の名称の経緯
日本毒科学会設立にあたって、学会の名称としていくつかの候補があった。医学関係者からは、病理、生理、薬理などにならって「毒理」が提唱された。その他、「毒物学」、「安全性学」、「中毒学」などが議論されたが、どれもトキシコロジーの一面のみを表すことから、結局「毒科学」に決まった。それから10年も経った頃に、この名称について、「毒」の研究は科学であり、それにさらに「科学」を重ねるのは会の名称としてふさわしくないとの議論があり、最終的にはToxicologyのカタカナ書きを採用し、1997年には学会の名称を「日本トキシコロジー学会Japanese Society of Toxicology(JST)」に改称した。さらに、2010年には学会の略称をJSTからJSOTに変更した。
その間、学会名の「トキシコロジー」は会員以外の分野の研究者にとってはその内容がよくわからないとの意見が多く出たため、2012年1月には、「日本毒性学会Japanese Society of Toxicology(JSOT)」に改名し今日に至っている。学会の名称はその集団の看板であるのでわかりやすい方が望ましい。企業では「毒性」という用語は後ろ向きの印象を与えるので使うのを躊躇する向きがあると聞いている。しかし、もし「日本安全性学会」にしたら交通安全と誤解されるかもしれない。その点、「日本毒性学会」は多くの人々が理解し易いことからよい結論だった。設立の翌年1982年3月の会員数は1083名であったが、2025年5月末現在では2667名(評議員335名、一般会員1995名、学生会員284名、名誉会員21名、功労会員32名)にまで成長し、米国Society of Toxicologyに次いで世界第2位の大きさにまで成長した。
4.学会誌の発刊
1)The Journal of Toxicological Sciences
1976年に日本毒作用研究会の機関誌として発刊したThe Journal of Toxicological Sciences(J. Toxicol. Sci.)は、日本毒科学会の設立後も学会の機関誌として今日まで毎月発刊されている。1976年1月に発刊された創刊号はB5版で、原著は僅かに4編だった。原著の第1号は田邊編集委員長の研究室の論文だったのも印象深い。J. Toxicol. Sci.の名称については、当時の学会の名称「毒科学」と同様に、“Toxicology”と“Sciences”は重複するのではないかとの議論があったが、最終的にJ. Toxicol. Sci.に代わる名称がなく今日に至っている。
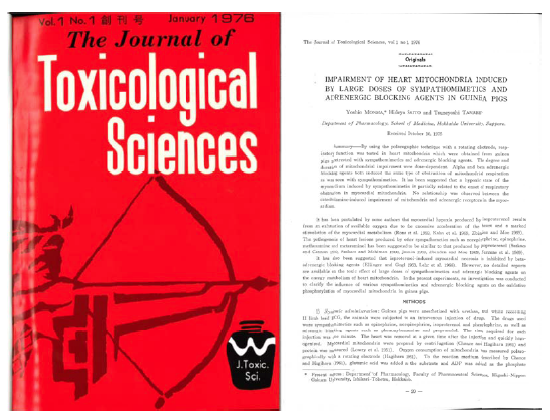
ここで米国SOTのジャーナルについて述べたい。1959年に毒性研究者の有志により Toxicology and Applied Pharmacology(TAAP、Academic Press)が発刊され、1961年にSOTの設立と同時に、機関誌として継続された。当時、TAAPは世界的に毒性関係で最も権威あるジャーナルだったので、米国の内外から投稿が殺到した。その後、1981年に第二の学会誌としてFundamental and Applied Toxicology(FAAT)が隔月に発刊された。1998年、SOTはFAATを“Toxicological Sciences(ToxSci)”に改名し、出版社もそれまでのAcademic PressからOxford University Pressに変えた。これらの大改革は初代EditorであるCurtis Klaassen教授の強力なリーダーシップによるものである。一方、TAAPは現在もAcademic Pressから刊行されているが、SOTのofficial journalとしての役目は2002年で終えた。現在はToxSciのみが学会誌として活躍している。小生はKlaassen教授の要請により2001年から2004年までAssociate Editor(Forum)をつとめた。投稿論文数が多すぎて、出版社との年間契約刷り上がりページ枚数内に絞るために論文の審査に苦労したことを憶えている。
興味あることに、“Toxicological Sciences”の書名はかつてJSOTの関係者が悩んだ“Toxicology”と“Sciences”との重複がそのまま使われている。つまり、1970年代にJSOT内で議論して決めた学会名の「毒科学会」、学会誌“J. Toxicol. Sci.”の選択は間違いではなかったことが証明された。余計な推測をするならば、SOTの“ToxSci”の名称は“J. Toxicol. Sci.”がヒントになったかもしれない。
歴代編集長(敬称略、所属は就任時)
田邊恒義(1976-1987)(北海道大学医学部)
菅野盛夫(1987-1993)(北海道大学医学部)
鎌滝哲也(1993-1996)(北海道大学薬学部)
仮家公夫(1996-1999)(神戸学院大学薬学部)
吉田武美(1999-2004)(昭和大学薬学部)
永沼 章(2005-2013)(東北大学薬学部)
鍜冶利幸(2014-現在) (東京理科大学薬学部)
2025年7月現在、Associate Editorは35名で6名が海外の研究者である。また、最近では海外からの投稿論文も多く、2019年の掲載論文の約60パーセントが海外の研究者で占められている。今後ともJ. Toxicol. Sci.が益々国際化することを期待したい。
2)Fundamental Toxicological Sciences
2014年7月のJSOT理事会において、第二の学会誌として新たにFundamental Toxicological Sciences (Fundam. Toxicol. Sci.)を発刊することが承認された。初代編集長には永沼章教授(東北大学薬学部)が就任された。本誌は毒性学の研究領域のすべてを対象とし、他誌に未発表で独創的な研究成果を掲載するオープンアクセスの電子学術雑誌である。投稿論文はすべて予めネイティブスピーカーによりチェックされた英文のみに限り、peer reviewされた後に、投稿日から原則として2週間以内に採否を決定する。採用された論文については、掲載料が支払われた論文を順次ウェブサイトに公表することとなっている(詳細はFundam. Toxicol. Sci.「投稿規定」を参照)。
5.認定トキシコロジスト制度(DJSOT)
1997年、日本毒科学会では、トキシコロジストのモチベーションを高め、その質の向上を図るために、資格認定試験制度の導入を検討した。また、第1回の試験を実施するにあたって、それまで大学、企業などで毒性、安全性の分野で多くの経験を持つ専門家の中から99名のGrandfatherを理事会で選出し問題作成にあたった。その結果、第1回の認定制度資格試験では受験者119名の内49名が合格し、Grandfather 99名を含めて148名が第1回“DJSOT”と認定された。さらに2002年には第1回資格更新が行われ、Grandfatherも他のDJSOTと同様に試験問題を回答し69名が更新した。2025年5月末現在、DJSOTは654名(内Grandfather 3名)である。DJSOTはDABT(Diplomate of the America Board of Toxicology)、ERT (European Register of Toxicologist)と共に国際的に高い評価を得ている。2014年6月には認定トキシコロジストとして長年毒性学の進歩発展に貢献した者に「名誉トキシコロジスト Emeritus DJSOT」の称号を与える制度が設けられた。2025年5月末現在、該当者数は66名である。
6.国際学会との連携
1)International Union of Toxicology(IUTOX)
JSOTの最初の国際的参画はIUTOXへ役員を送り出したことだった。IUTOXは1977年に欧米の毒性学者が中心となって設立された国際機関である(詳細はIUTOXホームページ参照)。設立に先立って、1975年にフランスのMontpellierで開催されたEuropean Society of Toxicology(EST)の年会において、SOTとESTの代表団により“International Toxicology Organization”の設立が決定された。それを受けて、1977年にカナダのTorontoにおいて、“1st International Congress of Toxicology(ICT-I)”が開催された。2nd Congress(ICT-II)は1980年にベルギーのBrusselsで開催され、そこで、国際トキシコロジー連合International Union of Toxicology(IUTOX)設立のために15名の委員からなる設立準備委員会が設置された。我が国からは白須泰彦博士(当時、(財)残留農薬研究所長)が参加した。IUTOX設立当初の加盟学会は9学会である(英国、EUROTOX、フィンランド、フランス、日本、カナダ、インド、米国、スウェーデン)。 その後世界各国から多くの学会がメンバーとなり、2025年現在55学会が加盟している。
(1)理事会 Executive Committeeの構成
初代理事会メンバーは設立当初に加盟した9学会から選出された。初代PresidentにはDr. S.L. Friess(米国)が就任し、日本からは、理事として池田正之教授(当時、東北大学医学部)が参加した。設立から2015年までに日本毒性学会からIUTOX Executive Committeeメンバーとして参画した代表は下記の通りである(敬称略)。
池田正之(Director)(1980-1983)
酒井文徳(2nd Vice President)(1983-1986)
福田英臣(2nd Vice President)(1986-1989、1989-1992)
佐藤哲男(2nd Vice President)(1995-1998、1998-2001)
黒川雄二(2nd Vice President)(2001-2004):2003年に都合により辞退したので、残余期間を佐藤哲男が代行した。
井上 達(2nd Vice President)(2004-2007、2007-2010):(2009年に都合により退任したので菅野 純が残任期間を継承した)
菅野 純(Vice President)(2009-2010、2010-2013)
菅野 純(President-Elect)(2013-2016)
菅野 純(President)(2016-2019)
熊谷嘉人(Director)(2019-2022)
広瀬明彦(Director)(2022-2025)
(2)国際会議の開催
IUTOXが主催する International Congress of Toxicology(ICT)は3年毎にIUTOX member societyの中から立候補し、投票によりホスト学会が選出される。我が国では、1986年に当時IUTOX Vice Presidentであった酒井文徳教授(東京大学医学部)が ICT-IVのPresidentとなり、東京において盛大に開催された。ICT-IVには世界各国から約1100名が参加した。余談であるが、IUTOX設立当初はICT開催に立候補する学会がなくて、IUTOX理事会において酒井教授が日本での開催を懇願されたと聞いている。最近は立候補学会が多く激戦である。1986年以後アジア地域ではICTの開催はなかったが、2013年に韓国ソウル市においてICT-XIIが開催された。
ICT 開催地(1977-2025)
1st(1977):Toronto(Canada)
2nd(1980):Brussels(Belgium)
3rd(1983):San Diego(USA)
4th(1986):Tokyo(Japan)
5th (1989):Brighton(UK)
6th (1992):Rome(Italy)
7th(1995):Seattle(USA)
8th(1998):Paris(France)
9th(2001):Brisbane (Australia)
10th(2004): Tampere(Finland)
11th(2007): Montreal(Canada)
12th(2010): Barcelona(Spain)
13th(2013): Seoul(Korea)
14th(2016): Merida(Mexico)
15th(2019): Hawaii(USA)
16th(2022): Maastricht(Netherlands)
17th (2025): Beijing (China)
2)Asian Society of Toxicology(ASIATOX)
1987年から2年毎に日本毒科学会と韓国毒性学会による「日韓合同毒科学シンポジウム」が韓国と日本で交互に開催された。これがASIATOXの前身である。
第1回 1987年:ソウル
第2回 1990年:名古屋
第3回 1993年:ソウル
1992年に日本毒科学会と韓国毒性学会の代表者数名が、ローマで開催されたICT-VIにおいてASIATOX設立について会談した。長時間の議論の結果、学会設立に向かってアジア地域の毒性学研究者に呼びかけることとなった。1993年11月27日、ソウルにおいて開催された日韓合同シンポジウムにおいて、ASIATOX設立準備委員会が結成され、Co-Chairとして、Sang Dai Park教授(ソウル大学)と柳田知司博士(当時、実験動物中央研究所)が選出された。当日の準備委員会の出席者は15名だった(韓国6、日本7、台湾1、シンガポール1)
(1)ASIATOX の設立
1994年6月8日に札幌において開催された日本毒科学会年会のときに、アジア各国の毒性学会の代表者16名が発起人となりASIATOXが設立された。当日の各国からの代表者人数は下記の通りである。日本8、韓国3、中国2、台湾2、タイ1。
設立時の加盟学会
Japanese Society of Toxicology
Korean Society of Toxicology
Chinese Society of Toxicology
Thai Society of Toxicology(formerly Toxicological Society of Thailand)
Toxicology Society of Taiwan
設立時役員(1994-1997)
President: Tomoji Yanagita(Japan)
1st Vice President: Sang-Dai Park(Korea)
2nd Vice President: Jion Lin Zhou(China)
Secretary General: Tetsuo Satoh(Japan)
Treasurer: Kyu-Hwan Yang(Korea)
Auditors: Jen-kun Lin(Taiwan), Songsak Srianujata(Thailand)
Councilors: Hitoshi Endou(Japan), Yong-Soon Lee(Korea), Ming-Dao Wang(China), Il-Moo Chang(Korea), Palarp Sinhaseni(Thailand)
その後、2012年にIranian Society of Toxicology、2014年にToxicology Society of Singapore、2018年にMalaysian Society of Toxicologyが加盟し現在に至っている。
(2)ASIATOX 役員
紙面の都合でPresident以外はJSOT選出役員のみを記載する(敬称略、所属は就任時)。
President: 柳田知司(実験動物中央研究所)
Secretary General: 佐藤哲男(千葉大学薬学部)
| Councilors: | 唐木英明(東京大学農学部) |
| 高橋道人(国立衛生試験所) | |
| 遠藤 仁(杏林大学医学部) |
President: Il Moo Chang(韓国)
Treasurer: 唐木英明(東京大学農学部)
| Councilors: | 遠藤 仁(杏林大学医学部) |
| 佐藤哲男(千葉大学薬学部) | |
| 高橋道人(国立医薬品食品衛生研究所) |
President: Songsak Srianujata(タイ)
Advisor(President 指名): 佐藤哲男(千葉大学薬学部)
Councilors: 資料なし
President: Jun-Shi Chen(中国)
2nd Vice President: 遠藤 仁(杏林大学医学部)
| Councilors: | 堀井郁夫(ファイザー(株)) |
| 津田修二(岩手大学農学部) | |
| 長尾 拓(国立医薬品食品衛生研究所) | |
| 沢田純一(国立医薬品食品衛生研究所) | |
| 遠山千春(東京大学医学部) | |
| 山添 康(東北大学薬学部) |
President: Jou-Fang Deng(台湾)
1st Vice President: 永沼 章(東北大学薬学部)
| Councilors: | 金井好克(杏林大学医学部) |
| 菅野 純(国立医薬品食品衛生研究所) | |
| 眞鍋 淳(第一三共(株)) | |
| 遠山千春(東京大学医学部) |
Advisor(President 指名): 佐藤哲男(千葉大学薬学部)
President: 永沼 章(東北大学薬学部)
Secretary General: 熊谷嘉人(筑波大学医学医療系)
| Councilors: | 堀井郁夫(ファイザー(株)) |
| 吉田武美(昭和大学薬学部) | |
| 遠山千春(東京大学医学部) | |
| 菅野 純(国立医薬品食品衛生研究所) | |
| 眞鍋 淳(第一三共(株)) |
President: Myung-Haing Cho(韓国)
Treasurer: 熊谷嘉人(筑波大学医学医療系)
| Councilors: | 堀井郁夫(ファイザー(株)) |
| 菅野 純(国立医薬品食品衛生研究所) | |
| 遠山千春(東京大学医学部) | |
| 吉田武美(昭和大学薬学部) | |
| 眞鍋 淳(第一三共(株)) |
Advisor(President 指名): 佐藤哲男(千葉大学薬学部)
President: Songsak Srianujata(タイ)
| Councilors: | 堀井郁夫(ファイザー(株)) |
| 北嶋 聡(国立医薬品食品衛生研究所) | |
| 熊谷嘉人(筑波大学医学医療系) | |
| 吉田武美(薬剤師認定制度認証機構、昭和大学名誉教授) | |
| Auditors: | 中村和市(北里大学獣医学部) |
| 熊谷嘉人(筑波大学医学医療系) |
President: Lijie Fu(中国)
| Councilors: | 菅野 純(日本バイオアッセイ研究センター) |
| 広瀬明彦(国立医薬品食品衛生研究所) | |
| 小椋康光(千葉大学薬学部) | |
| 田口恵子(東北大学大学院医学系研究科) | |
| 熊谷嘉人(筑波大学医学医療系) | |
| Auditor: | 熊谷嘉人(筑波大学医学医療系) |
| President: | Jih-Heng Li (台湾) |
| Treasurer: | 鍜冶 利幸(東京理科大学) |
| Councilors: | 菅野 純(国立医薬品食品衛生研究所) |
| 広瀬明彦((一財)化学物質評価研究機構) | |
| 小椋康光(千葉大学大学院薬学研究院) | |
| 田口恵子(東京大学大学院農学生命科学研究科)Liaison of JSOT | |
| 熊谷嘉人(九州大学大学院薬学研究院) |
(3)International Congresses of ASIATOX(会長、開催期日、開催地)
原則として3年ごとにmember societiesの持ち回りで開催されていた。その後、2018年にタイで開催されたASIATOX-VIII総会において、2年ごとに開催されることとなったので、ASIATOX-IXは2020年に中国の杭州において開催された。その後、2023年の台湾で開催された10th Congressにおいて、ICTの開催年と重複する可能性があるとの意見があり、11th以後は3年ごとに開催されることとなった。
1st: 柳田知司, June 29-July 2, 1997, 横浜, 日本
2nd: Il-Moo Chang, August 23-25, 2000, Jeju-Do, Korea
3rd: Songsak Srianujata, February 1-6, 2004, Bangkok and Chiang Mai, Thailand
4th: Jun-Shi Chen, June 18-21, 2006, Zhuhai, China
5th: Jou-Fang Deng, September 10-13, 2009, Taipei, Taiwan
6th:永沼 章, July 17-20, 2012, 仙台, 日本
7th: Myung-Haing Cho, June 23-26, 2015, Jeju, Korea
8th: Songsak Srianujata, June 17-20, 2018, Thailand
9th: Lijie Fu, September 23-26, 2020, Hangzhou, China
10th: Jih-Heng Li, July 17-20, 2023, Taipei, Taiwan
11th: Rozaini binti Abdullah, August 3-6, 2026, Kuala Lumpur, Malaysia
アジア地域には農薬毒性や環境汚染物質など多くの問題が残されているので、今後もトキシコロジストの役割が益々期待される。
7.おわりに
我が国では、会社や大学の定年の年になると殆んど例外なく職場を離れる。定年後の生活は個人により大きく違うが、それについて他人がとやかく言うことではない。私の場合、講義と研究に追われ、加えて学内、学部内の会議など毎日が激戦だった。その頃、厚生省勤務の友人が「毎日がモグラたたきの連続だよ」と言った言葉が忘れられない。毎日起こる出来事を追っかけるのに精一杯で、新しいことを考える余裕がないのだ。
若手研究者の皆様も毎日の仕事に追われていると思うが、是非「あそび」を持って欲しい。これは「遊び」ではなく「余裕」である。「ゆとり」の方がより適切な日本語であるが、昨今の日本ではこの言葉の印象が極めて悪い。車の運転でも同じだ。ハンドルに「あそび」がなければ、危険きわまりない。
米国の大学教授には停年がない。しかし年長の教授にとって急速に進んでいる最先端の研究レベルを維持するのは至難のわざだ。ここで私が尊敬する楢橋敏夫先生との想い出を述べさせて頂く。先生は1948年に東大農学部をご卒業後、1961年にシカゴ大学医学部に留学し、そのまま半世紀を超えてデューク大学医学部やノースウエスタン大学の医学部薬理学教室の主任教授を歴任された。その間、農薬やテトロドトキシンを初め多くの毒物の毒性発現のメカニズムを膜イオンチャネルの遮断で明快に解明し、神経毒性学の分野で輝かしい業績を挙げられた。
2000年頃だったと記憶するが、米国SOT年会会場で、突然「日本の方ですか」と声をかけられた。楢橋先生とは初対面だったが、話し好きな先生は何十分でも立ち話をした。2010年に私がSOT教育賞を受賞したときには、授賞式の終了後にわざわざ「御目出度うございます」と声をかけて頂き恐縮した。そのときに、先生は、「最近は分子レベルの仕事でないとNIH Grantの様な大きな研究費はとれないですね」と言われていた。また、「若い研究者は遺伝子の研究が好きなので、皆さんそちらの研究室に移るので私のところは大変ですよ」と嘆かれていた。大御所の先生がこのような悩みがあることを知って複雑な気持ちになった。それまで国際的に確固たる業績を挙げられた先生でも、現在の研究業績で評価されるのが米国の厳しい現実である。その後も毎年SOT年会でお会いしたが、2013年のSOT年会ではお見かけしなかった。ご高齢なのでどうされたかと思っていたら、SOTからの情報で2013年4月21日にご逝去されたことを知った。86歳だった。Bruce AmesやJohn Doullと並んでSOTの顔でもあった楢橋先生を失ったことは国際的に大きな損失である。
さて、若手研究者は国際的な動きを高いアンテナで追跡することが必要だ。常に心の中念じているとチャンスが到来する。それを引き込む力がactionであり、actionがあればre-actionが生まれる。さらに、仕事を効率的に進めるために、恩師、上司、同僚との出会いを大事にして欲しい。人とのつながりは生涯にとって大きな財産となる。私事で恐縮であるが、新しい仕事を立ち上げるためには、「三心」が必要だ。それは、「発心」、「決心」、「持続心」である。これを座右の銘として50年が過ぎた。若手研究者の皆様も是非目の前の難関にくじけることなく日々精進して貰いたい。
この小文をまとめるにあたって、これまで半世紀を超えてお世話になった多くの恩師、友人、知人、さらに私の研究を支えてくれた同僚、教え子など多くの人々のことを想いだした。その関係は現役を離れた今でも続いている。最近の私にとっては、若い人との出会いが新しいエネルギーとなっている。先人が道を切り開いてくれた我が国の毒性学は、今後とも、若手研究者に引き継がれてさらに発展するものと信じている。最後に、JSOTが世界のトップリーダーとして今後もますます飛躍することを祈念して筆を擱く。
謝辞:今回の小文をまとめるにあたって、JSOTに関する資料を提供して頂いた事務局の皆様に心から御礼を申し上げる。また、2025年の更新にあたって多くのご助言を頂いた諸先生に深謝する。
佐藤哲男
千葉大学名誉教授
日本毒性学会名誉会員
(2015年3月)
(2020年1月、2022年9月、
2025年7月更新)