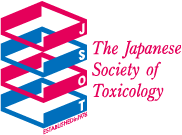コミュニケーション/毒性研究者紹介
毒性研究者紹介
第52回学術年会
優秀研究発表賞受賞者
塩野義製薬株式会社
科研製薬株式会社 新薬創生センター 薬物動態・安全性部 安全性グループ
群馬大学大学院医学系研究科応用生理学分野
東北大学大学院薬学研究科代謝制御薬学分野
花王株式会社
学生ポスター発表賞受賞者
東京大学農学部獣医学専修 獣医薬理学研究室
北里大学 獣医学部獣医学科
東北大学農学研究科動物生殖科学分野
東北大学薬学研究科衛生化学分野
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 薬効解析学
東北大学大学院薬学研究科衛生化学分野
東北大学大学院 代謝制御薬学分野
広島大学大学院 医系科学研究科 生体機能分子動態学研究室
大阪大学大学院薬学研究科 分子生物学分野
岡山理科大学大学院理工学研究科 自然科学専攻生命科学コース
第51回学術年会
優秀研究発表賞受賞者
富山大学 研究推進機構 研究推進総合支援センター 生命科学先端研究支援ユニット 分子・構造解析施設
富山大学 学術研究部 薬学・和漢系 ゲノム機能解析研究室
九州大学大学院薬学研究院 薬物動態学分野
静岡県立大学 薬学部 生体情報分子解析学分野
徳島文理大学 大学院薬学研究科 衛生化学分野
中外製薬株式会社TR本部安全性バイオサイエンス研究部
第一三共株式会社 安全性研究所
国立医薬品食品衛生研究所 病理部
中外製薬株式会社 トランスレーショナルリサーチ本部 安全性バイオサイエンス研究部
学生ポスター発表賞受賞者
千葉大学 予防薬学研究室
九州大学大学院薬学研究院薬物動態学分野
東京大学大学院 農学生命科学研究科 獣医衛生学研究室
東北大学大学院 薬学研究科 代謝制御薬学分野
山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部 衛生化学分野
岐阜薬科大学 衛生学研究室
京都大学iPS細胞研究所
東京大学大学院薬学系研究科 分子薬物動態学教室
第50回学術年会
優秀研究発表賞受賞者
東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学研究室
金沢大学 医薬保健研究域薬学系 薬物動態学研究室
東京大学大学院薬学系研究科 分子薬物動態学教室
協和キリン株式会社 トランスレーショナルリサーチユニット 安全性研究所
学生ポスター発表賞受賞者
所属
塩野義製薬株式会社
名前
石井 裕也
受賞タイトル
in vitro肝障害パネル評価を活用した臨床肝障害予測モデルの構築
臨床での薬剤誘発性肝障害(DILI)リスクを予測するための評価系構築を目的として、複数のin vitro実験結果を取得し、それらの結果を元に高精度にDILIリスクを予測する機械学習モデルの構築に成功しました。先行研究で使用されていたin vitro実験の細胞種を変更する等の改善を施すことで予測精度が向上しました。また構築された予測モデルにおける各in vitro実験の寄与度を解析することで、HepaRG細胞による肝スフェロイド細胞毒性実験と臨床薬物曝露量を組み合わせた値が、本予測モデルにおいては最も優れたパラメータであることも明らかにしました。
バイオインフォマティクス研究室にて、標的分子に高親和性なアプタマー配列を取得するための分子進化法であるHigh-throughput systematic evolution of ligands by exponential enrichment(HT-SELEX)から得られる大量の配列データを解析し、高親和性アプタマーを同定するための解析アルゴリズム開発を目指していました。具体的には、配列情報だけでなく、アプタマーの性質に重要である構造情報も考慮して解析する先行手法がありましたが、先行手法では考慮出来ていないとある特殊な構造も考慮して解析することで、先行手法では見逃してしまう高親和性アプタマーを同定出来るアルゴリズムに拡張しようと研究を進めていました。
祖母が医薬品の副作用で亡くなってしまった経験より予期せぬ医薬品の副作用で亡くなる人を無くしたいと考え、安全性研究を志望し、入社しました。
当初は、オミクスデータ解析等を通した情報科学的な観点から一定の毒性予測が出来るのではないかと考えていました。しかし、現在では取得できるデータに限りがあることや仮に解析結果を得たとしてもその結果の妥当性を判断して、前向きに毒性予測することの難しさを感じています。
大変だったことは、大学時代の研究と比較すると少ないデータで解析・解釈をする必要があったこと、また異なる性質を持つデータ(例えば生化学検査のような数値データから病理検査の所見名等)を包括して考えなければならなかったことです。一方で、in vitro等のデータから、生体で起きていることを考察し、その考察をサポートするような結果が得られた時はとても面白かったです。
現在はin vitro実験以外から得られる、例えば化合物の構造情報等の情報も活用したin silico肝障害予測に興味を持っています。また将来の夢は、臨床におけるidiosyncratic毒性を非臨床研究の段階で予測できるアプローチの確立です。
「石の上にも三年」
入社時にトレーナーとして、毒性学の基礎について指導くださり、本研究についても多大なサポートをいただいた、加藤祐樹氏に感謝申し上げます。右も左も分からない中、手厚いサポートをしていただけたおかげで、現在でも毒性領域に身を置いて研究を続けられています。
毒性学は学際領域のため、必要となる背景知識も多いですが、その分色々な背景の研究者と関われるのも魅力だと思います。自分に足りない知識があればそれを得意とする人と協力して、逆に自分が得意な所があれば協力して、研究を続けていってもらえたらと思います。
所属
科研製薬株式会社 新薬創生センター 薬物動態・安全性部 安全性グループ
名前
衣斐 彼方
受賞タイトル
ラットの摘出精巣を用いたアゾール系化合物の雄性ホルモン産生への影響評価
抗真菌作用を有するアゾール系化合物は雄性ホルモン産生阻害作用が示唆されており、人体及び環境への影響が懸念されています。今回、ラットの精巣切片を用いた評価法でアゾール系化合物による雄性ホルモン産生阻害作用のメカニズムに関する情報を取得しました。
獣医病理学研究室に所属し、臨床検体の病理診断及び養鶏場におけるアミロイドーシスの集団発生の原因究明を行っていました。
製薬メーカーに入社し、化合物による様々な毒性変化の誘発機序解明に関わるようになったことです。
当初、薬理作用の延長上に毒性があるという認識を持っており、毒性試験で見られる変化はいずれも予想可能なものだろうと考えていました。しかし、実際にはオフターゲットによる影響、化合物による一般状態悪化に伴う二次的変化といった要素が複雑に絡み合って所見として現れるケースが多々あることを知りました。毒性研究は難しいと感じますが、その一方であらゆる知識・経験を総動員できる非常にやりがいのある分野であると感じています。
短期の反復投与試験で毒性か非毒性か迷う所見を経験しました。各種パラメータとの比較、文献調査や意見聴取を経て最終的な判断を下しましたが、非常に大変だったと感じました。一方、同試験結果から長期投与での変化を予想し、その通りの結果が出た際は非常に嬉しかったです。まだ弱卒ですが、毒性研究の醍醐味はこういうところになるのかもしれないと感じました。
薬物動態に興味をもっています。毒性を解釈する上で薬物動態の知識は必須と感じており、今後学んでいければと考えております。最終的には各分野に精通し、複合的な視点で毒性を評価することができる専門家を目指したいです。
吉田松陰の「一日一字を記さば、一年にして三百六十字を得る。」です。何事も継続することを大事にしたいと考えています。
研究者としてはもとより、人として成長できるよう親身になってご指導いただいた大学研究室の教授に心から感謝しております。引き続きご指導・ご鞭撻の程どうぞ宜しくお願い致します。
毒性の解釈には、毒性学の知識はもとより、薬理、薬物動態、製剤等の多領域に渡る知識が必要な場面が多いと感じます。ぜひ、ご自身の専門以外の領域にも積極的に取り組んでください。
所属
群馬大学大学院医学系研究科応用生理学分野
名前
藤原 悠基
受賞タイトル
甲状腺ホルモン変換酵素DIO2を介したペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)による新たな発達神経毒性メカニズム
有機フッ素化合物の代表的な一種であるPFOSの甲状腺ホルモン系を介した発達神経毒性メカニズムの一つとして甲状腺ホルモン変換酵素であるDIO2を介した影響を報告し、受賞しました。この報告にあたり群馬大学重粒子医学研究センター宮坂勇平先生と元群馬大学応用生理学の岩崎俊晴先生、鯉淵典之教授をはじめとした共著者の皆様に重ねて御礼申し上げます。
学部1年~3年は有機合成系の研究室で抗酸化物質や抗がん剤、学部4年では抗酸化物質と糖尿病の関連性、大学院から現在にかけては発達神経毒性を中心に研究を行っています。臨床では腎・泌尿器系が専門のため化学物質による腎機能への影響に関する研究も開始したところです。高校時代はSSH(スーパーサイエンスハイスクール)でHPLCでの分析に加え風力発電や建築の研究もしていました…
熊本大学大学院の講義で指導教官でもあった加藤貴彦先生のお話をお聞きし、学部生時代にはとらえきれなかった環境因子の重要性を再認識し、携わってみたいと感じたことです。
すでに市場に出ている化学物質は様々な毒性試験をパスしてきたのになぜ研究する必要があるのか?と考えていました。しかし、過去や現在だけでなく今後出てくる化学物質をより安全にヒトが利用できるための研究をしていると考えるようになり、やりがいを感じています。
毒性影響を捉えてもそのメカニズムに迫ることが難しいことが多々あり、大変な思いをしてきました…。ただ、メカニズムが明らかになった時には閾値の設定などヒトと化学物質の共存に繋がると思いますので、面白いと感じます。
開発者、毒性評価者、研究者、一般の皆さんが納得できる評価系を確立出来たらと思います。また、このような毒性研究を通じて薬を含めた化学物質の安全利用に繋がれば嬉しいです。
Paracelsusの“All substances are poisons : There is none which is not a poison.”
熊本大学大学院の院生の頃より私をご指導いただいた、現 弘前大学大学院保健学研究科教授の宮崎航先生です。先生がおっしゃった、「生まれてくる子供たちのために…」この先生の言葉で私は毒性研究に進むことを決めました。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
周りの先生方や同僚に支えられて今回の賞をいただくことが出来たと思います。毒性の評価系は一人だけが可能な特殊な評価系が良いのではなく、全員が同じ系を実践でき、同じ評価結果となることがもっとも良い系と考えています。そのような評価系の立ち上げをいつかご一緒できると嬉しいです。
所属
東北大学大学院薬学研究科代謝制御薬学分野
名前
髙島 隼人
受賞タイトル
メチル水銀によるセレン代謝阻害とPRDX6を介したフェロトーシス感受性制御
今回我々は、メチル水銀曝露によるセレノプロテイン発現低下機構に関して、セレン代謝酵素への付加体形成に着目して研究を行いました。その結果、メチル水銀がペルオキシレドキシン6(PRDX6)に対する親電子修飾を介して酵素活性を阻害すること、またPRDX6がメチル水銀により誘導されるフェロトーシスの感受性決定因子であることを見出しました。
セレンの代謝に焦点を当てて研究しています。学部生時代は一酸化窒素を、大学院ではメチル水銀を用いて、親電子物質によるセレン代謝攪乱メカニズムの解明を目指しています。
現在の研究室に配属されたことがきっかけです。
研究を始めた当初は、分からないことばかりでとりあえず指示されたことをする、という感じでしたが、現在では自分でも少しずつアイデアを出せるようになり、何より研究を楽しめるようになりました。
毒性研究に限った話ではないですが、自身の仮説と異なる結果が出てきたとき、「どうしよう…」と思う反面、「想定できていなかった新たな知見があるのでは?」という期待ができることに面白さを感じています。
これからもセレンに触れた研究を行いたいと考えています。
所属研究室の斎藤芳郎先生、外山喬士先生に日々支えていただいています。自分の興味の赴くままに研究を行える環境をいただき、心より感謝しています。
指導教員である外山喬士先生にこの場をお借りして感謝申し上げます。先生の背中を見て研究の楽しさに気づき、研究者という選択肢を考えるようになりました。何かにつけて迷惑をかけてばかりの日々ですが、今後ともよろしくお願いいたします。
何をするにも健康が一番です。無理せず頑張ってください。
所属
花王株式会社
名前
清水 庸平
受賞タイトル
新奇高感度検出試薬を用いた微量皮膚感作性物質のリスク評価と感作源特定を目指した代替法開発
既存の皮膚感作性代替法の課題である、微量感作性物質の高感度検出と感作源の構造解析の2つを実現可能にする新規の代替法開発に取り組んでおり、今回は新奇高感度検出試薬の開発と感作性物質との反応性、得られた付加体の構造解析事例について発表しました。
放線菌や糸状菌の2次代謝産物からピロリ菌の特異的阻害剤を探索し、分子構造解析する研究を行っていました。また、大学院時には1次代謝酵素の機能解析も行っていました。
入社してから、今回発表したテーマに取り組むようになったことがきっかけです。
複雑な要素が絡み合っており、難しそうという印象でした。現在もその印象は変わっていません。
開発している手法が新規手法のため、学会などでの反応や社内での応用事例の検討などは非常にわくわくします。一方で、特に感作源の構造解析については難しいケースも多いので苦労することが多いです。
現在開発している手法を様々な原料や素材に適用できる手法に完成させることです。
毒性研究の発展に貢献したいです。
「自彊不息」
研究テーマの先輩へ
入社以来、同じテーマに取り組ませていただき、議論したり夢を語ったりしながら楽しく研究できています。どんなときも冷静で論理的に進められる先輩を尊敬しています。少しでも追いつけるよう頑張ります。これからもよろしくお願いします。
失敗を恐れず自由な発想で研究に取り組んで欲しいと思っています。また社内にとどまらず、学会や研究会などさまざまな場で積極的に発表に挑戦し、多様な研究者と議論を交わして視野を広げてください!
所属
東京大学農学部獣医学専修 獣医薬理学研究室
名前
岡本 雄揮
受賞タイトル
代謝機能障害関連脂肪性肝炎(MASH)に続発する肝性骨異栄養症の発症機序の解明
慢性肝疾患は様々な臓器で合併症を引き起こすことが知られています。その中でも、骨密度低下を特徴とする肝性骨異栄養症は発症機構が不明であり、明確な治療法がありませんでした。今回は慢性肝疾患のうち代謝機能障害関連脂肪性肝炎(MASH)に伴う肝性骨異栄養症にFGF23が関与している可能性を明らかにしました。
MASHに関する研究をしています。その中でも合併症となる肝性骨異栄養症や臓器連関に着目して研究を進めています。
獣医学を通じて薬剤の薬理、毒性や疾患の治療標的を研究する獣医薬理学研究室に配属されたことがきっかけです。研究を進めるにつれ、高脂肪食が肝臓に与える毒性やMASHにより体内で産生される物質が生体に与える影響について興味を持ちました。
始めた当初は右も左もわからずとりあえず実験をしているだけでしたが、進めるにつれて得られたデータに対し、次にどういった事項を検討するかを考えられるようになりました。
薬理と毒性は紙一重だと考えています。何らかの物質が生体に与える影響は考え方によって、薬理とも毒性とも捉えられることが面白いと感じています。
生体全体に対する毒性を考えた上で疾患の治療標的を見出せるような研究をすることで、人々の役に立ちたいです。
当研究室の堀正敏先生、三原大輝先生に研究の指導から研究室での日常まで大変お世話になりました。また研究室員のみなさんのおかげで楽しく研究室生活を送ることが出来ています。
ご指導いただいている三原大輝先生にこの場を借りて感謝を伝えたいです。配属当初、生物に関する基礎知識すらおぼつかなかった自分の意見を否定することなく、ゆっくり研究を見守っていただきました。
私自身、研究者として道半ばです。これからも共に頑張りましょう。
所属
北里大学 獣医学部獣医学科 毒性学研究室
名前
深松 美咲
受賞タイトル
リトコール酸骨格を持つ新規ビタミンD受容体アゴニストDcha-20の殺鼠効果及び毒性発現機序の探索
本研究では、ビタミンD受容体の新規アゴニストDcha-20の殺鼠効果および作用機序を検証しました。Dcha-20はSDラットにおいて強い致死性を示すとともに、従来の殺鼠剤と比較して短い半減期を有し、二次中毒リスクの低減が期待される有用な動態を示しました。また、腎・腸管障害を介したCa非依存的な致死機序が関与している可能性が示され、新規作用機序を持つ殺鼠剤候補であることが示唆されました。
殺鼠剤についての研究をしています。研究室では複数動物種におけるビタミンKアンタゴニスト型殺鼠剤の薬物動態/薬力学(PK/PD)予測や、新規ビタミンD受容体アゴニスト型殺鼠剤候補化合物の毒性評価に取り組んできました。
今所属している毒性学研究室に入ったことがきっかけです。世の中に存在する様々な物質の安全性を確認し、人々の健康や生活を陰ながら支えるという姿勢に魅力を感じてこの分野に興味を持ちました。
研究を始めた当初は、水銀やヒ素のような「毒らしい毒」を扱うのかなと思っていましたが、実際には殺鼠剤やインクなど、身近な物質を対象にしていることに意外さを感じました。殺鼠剤はまだ危険な印象がありますが、成分の一つであるワルファリンは医薬品としても使われており、同じ物質でも使い方次第で毒にも薬にもなることを毒性研究を通して実感しました。
AIやシミュレーションを用いた研究を行うこともあるのですが、それらの結果を生体レベルの現象に結びつけて理解することに、難しさと同時に大きな面白さを感じています。
病理と生化学に関する知識を深めたいと考えています。今回の研究で毒性と病理は切っても切り離せない関係にあると痛感し、まだ学び始めたばかりではありますが、基礎から理解を深めつつ技術的にも研鑽を積んでいきたいと思っています。また、化学構造が代謝や毒性発現に大きな影響を与えることも改めて実感したので、この分野についても知識を深め、広い視野で物事を見ることができる研究者を目指したいと考えています。
日々熱心にご指導くださっている当研究室の鎌田亮先生、武田一貴先生に、この場をお借りして心より感謝申し上げます。また、同期をはじめとする研究室メンバーのおかげで、充実しつつも笑いの絶えない研究ライフを送ることができています。これからも周囲への感謝の気持ちを忘れずに、研究に励んでいきたいと思います。
現在ご指導いただいている武田一貴先生に、改めて感謝の気持ちをお伝えしたいです。先生に研究のいろはや毒性学の面白さを教えていただいたおかげで、研究者を志すようになりました。まだまだ未熟で、至らぬ点も多くあるかと思いますが、精いっぱい頑張っていきたいと思いますので引き続きご指導のほどよろしくお願いいたします。
研究に真摯に取り組む後輩のみなさんからは、いつも大きな刺激と元気をもらっています。毒性学は奥の深い学問であり、同じ分野の研究でもそれぞれ異なる視点や強みを持っているため、私自身も学ばせていただくことが多くあります。今後も同じ研究に携わる仲間として、心身の健康を大切にしながら共に成長し、頑張っていきましょう。
所属
東北大学農学研究科動物生殖科学分野
名前
加来 建之
受賞タイトル
生後発達期におけるグルホシネートの急性曝露が成熟後の脳高次機能に及ぼす影響
本研究では、除草剤成分グルホシネート(GLA)を異なる発達段階のマウス(幼若期、性成熟期、成熟期)に急性曝露し、成熟後の行動様式を解析しました。その結果、生後発達期に曝露されたマウスでは短期記憶の形成・定着効率が低下することを明らかにしました。
これまでGLAの中毒事故による成人での神経症状は多く報告されてきましたが、発達期曝露が中枢神経系の発達に及ぼす影響は未解明でした。本研究の成果はこの知見の空白を埋めるとともに、GLAを含む農薬の適切な使用と管理の重要性を示すものです。
環境中の化学物質曝露が中枢神経系の発達に及ぼす影響を明らかにすることを目的に研究を進めています。農学部に所属していることもあり、特に殺虫剤や除草剤といった農薬を対象とし、マウスモデルを用いて行動学的、組織学的、および電気生理学的な解析を行っています。
指導教員である種村健太郎先生から提示していただいた研究テーマの中で一番取り組みたいと思ったのが、毒性学に関連する研究テーマでした。
研究を始めた当初は、毒性学は人や自然環境を守るうえで重要な領域であると漠然と感じていました。現在は、そのイメージがはっきりし、自身の担当する研究領域に対してより強い責任感を持って取り組めるようになったと感じています。
毒性学は、とりわけ『社会のあり方』に強い影響を及ぼす分野だと考えています。自分の研究成果が社会の仕組みづくりに寄与できる可能性を思うと大きなやりがいを感じ、それが研究の面白さにつながっています。
一方で、社会的影響の大きさゆえに私たちは強い責任感を持って取り組む必要があり、この点は大変に感じます。また、これまで取り組んできた行動試験は手技や環境条件の影響を受けやすい実験のため、試験中の環境整備が大変です。
現在は、国や地域ごとにおける化学物質やその毒性に対する価値観の違いに関心を持っています。幸いにも、東北大学に在籍しながら海外で1年間研鑽する機会をいただいており、在籍中に多様な価値観に触れ、研究の視野をさらに広げられることを期待しています。
将来の夢は未定ですが、若くて胃が元気なうちに世界中を旅して現地の料理を楽しみたいです。
指導教員の種村健太郎先生からいただいた「慌てず、急いで、正確に」という言葉は定期的に思い出して、実践するようにしています。まだまだミスは多いですが、この言葉のおかげでこれまで多くのミスを未然に防ぐことができました。
種村健太郎先生
いつも温かくご指導いただき、心より感謝申し上げます。先生のもとだからこそ、のびのびと研究に取り組むことができていると感じています。
毒性学を専攻している学部生、修士学生のみなさん
現在所属している農学研究科には毒性学を専攻している学生が少ないため、学会等で皆様とお話しできる機会を楽しみにしています。
所属
東北大学薬学研究科衛生化学分野
名前
小島 諒太
受賞タイトル
トランス脂肪酸による細胞老化を介した炎症応答の促進機構
代表的なトランス脂肪酸であるエライジン酸がDNA損傷誘導時の細胞老化を亢進することを明らかにしました。エライジン酸は脂質ラフトに取り込まれることでIL-1受容体の集積を促進し、NF-kBシグナルを活性化することで炎症応答を惹起します。さらに、MAFLD病態モデルマウスにおいて、トランス脂肪酸が細胞老化を惹起していることも明らかにしました。
細胞内のシグナル伝達機構に注目し、生体が薬剤や活性酸素といったストレスに対するストレス応答として、炎症や細胞死を誘導する際の詳細な機構について解析を行っています。
細胞内ストレス応答機構についての研究を行っている研究室への配属がきっかけです。
研究室に配属される前には、「毒性」というと環境汚染物質のような「毒」のイメージが強いものを思い浮かべており、それらが人に与える悪影響や、疾患がもたらされる機構について解析を行っているという印象を持っていました。現在では、それだけではなく、治療のために使用される薬剤が副作用としてもたらす毒性の機序解明など、幅広いテーマを含んでいることを知り、その奥深さに興味を持っています。
細胞内で起こっている特定の現象について分子機構を詰めていく過程で、予想とは反する結果が出た時は、面白くもあり、大変でもあると感じます。結果を説明するための仮説を、文献を調べながら再考することは大変な作業ではありますが、実際に起こっている生命現象に一歩近づいたような感覚は研究の醍醐味であると思います。
細胞死に興味があります。特に近年では新しい誘導機構・形態の細胞死が報告されているので、その生理的意義や病理的な側面、既知の細胞死との関連を含め、詳細が明らかになってくると面白いと考えています。
座右の銘はないのですが、私を支えているのは両親や兄妹といった家族の存在です。研究者の道を志すことができたのは、両親の理解と助けがあったからです。自分が希望するままに好きな道に進ませてくれたこと、応援し支え続けてくれていることに対して、いつか恩を返せたらと思います。
日頃から親身にご指導くださる、東北大学大学院・薬学研究科・衛生化学分野の松沢厚先生、平田祐介先生に、心より感謝を申し上げます。特に私が所属する研究室内のグループで直接ご指導をいただいている平田先生には、研究の進め方からプレゼンテーションのコツまで、右も左も分からなかった自分を育ててくださったことに、深く感謝を申し上げます。
何をするにしても、健康第一です。適度に周囲とのコミュニケーションを取り、大変な時には誰かを頼って、一緒に頑張りましょう。皆様がそれぞれの分野でご活躍されることを願っております。
所属
岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 薬効解析学
名前
三木 崚平
受賞タイトル
メチル水銀曝露による精神症状関連部位の障害
メチル水銀中毒である水俣病では、運動・感覚機能の障害だけでなく、性格の変化や抑うつなどの精神症状も報告されています。一方で、精神症状を引き起こす責任病巣はいまだに明らかになっていません。本研究では、メチル水銀曝露マウスを用いて、大脳辺縁系の感情や意欲に関わる部位で神経脱落が生じていること、さらに障害部位では抑制性神経が選択的に障害を受けていることを明らかにしました。
メチル水銀によって引き起こされる毒性病態の理解を目指し、二つのアプローチで研究を進めています。一つは神経障害メカニズムの分子レベルでの解明、もう一つはこれまで見過ごされてきた障害部位の探索です。行動解析なども取り入れながら、病態の全体像を多角的に捉えることを目指しています。
所属研究室に配属されたことがきっかけです。学部生時代から一貫して環境化学物質による神経障害機構の解析に取り組んでおり、博士課程進学を機に国立水俣病総合研究センターへ出向する機会をいただきました。水俣での共同研究を通じて、特にメチル水銀に焦点を当てた研究を進めています。
一つの毒性病態を対象に、様々な解析手法を駆使して分子から個体まで多層的にアプローチできる点に、当初から魅力を感じていました。一方で現在は、選択肢が豊富であるからこそ、先行研究を丁寧に読み解いて病態の本質を見極める力や、未病段階における微細な変化を捉える観察眼の重要性を実感しています。
これまで見過ごされてきた、メチル水銀中毒における精神症状を病理学的に再解釈できた点が特に面白いと感じました。研究にあたり、水俣病発生当時の文献を精査すると、現代の研究にも活かせる貴重な臨床所見が数多く見出され、温故知新の重要性を実感しました。
生命現象を俯瞰的な視点から理解できる毒性研究者になることが将来の夢です。研究対象への深い理解と観察眼を持ち、病態の兆候を見落とさない姿勢を大切にしたいと考えています。モデルはあくまでも手がかりであり、その先にあるヒトの健康を見据えて研究に取り組むことで、毒性病態の体系的な理解に貢献していきたいです。
出向先でご指導いただいている、国立水俣病総合研究センターの藤村成剛先生です。昼夜を問わず研究に情熱を注ぎ、生命現象の追究を楽しむ姿に日々刺激を受けています。議論の際には私の意見にも真摯に耳を傾けてくださり、的確な助言をいただいています。先生の研究への情熱を持ち続ける姿勢は、若手研究者である私にとって大きな励みになっています。
学部配属から現在に至るまでご指導くださっている上原孝先生に、この場を借りて心より感謝申し上げます。水俣への出向の際にも背中を押してくださり、新たな挑戦に踏み出すことができました。常に多様な実験・発表機会を与えていただき、研究者として成長できる環境を整えてくださったことに深く感謝しています。これからもよろしくお願いいたします。
行き詰まったときこそ、視野を広げるチャンスです。他分野の研究に目を向けたり、周囲と話したりすることで、思わぬ突破口が見つかることもあります。研究は孤独な営みではなく、人とのつながりの中で育まれるものだと思います。互いに刺激し合いながら、一緒に頑張りましょう。
所属
東北大学大学院薬学研究科衛生化学分野
名前
大谷 航平
受賞タイトル
フェリチノファジーを利用した新規癌治療戦略の構築
フェロトーシスは鉄依存的な脂質過酸化により誘導される細胞死であり、癌細胞は細胞内鉄濃度が高いことから、フェロトーシス誘導により癌を選択的に排除する戦略が注目を集めています。しかし実際には、細胞内遊離鉄量が鉄貯蔵タンパク質により制限され、既知のフェロトーシス誘導剤のみでは抗腫瘍効果が不十分です。そこで我々は、細胞内遊離鉄を増加させる薬剤の探索によってポリペプチド化合物YMD424を新たに同定し、その作用機序を明らかにしました。
細胞内シグナル伝達に注目し、薬剤や環境中物質といったあらゆる外的ストレスにさらされた際、細胞がどのような応答をするかについて、詳細な研究を行っています。
細胞内シグナルの研究を行っている研究室への配属がきっかけです。
始めた時は「毒性 = 毒物」という、いわゆる危ないものに関して研究を行うという印象を持っていました。しかし、この分野に携わって研究を進めるうちに、あらゆる物質が毒性研究の対象となること、特に我々の体にとって良いものとして捉えられる薬までもが重要な研究対象であることを知り、現在では本分野の幅広さや奥の深さに興味を持っています。
基本的には予想通りの結果が得られることがまず無く、その度に新たなアイデアを生み出し、検証していくことが、大変でもあり面白いところでもあると感じています。
免疫関連、特に自然免疫による炎症の誘導に興味があります。自己免疫疾患や特に過剰炎症が原因となる疾患は、未だに万能な薬がないため、関連する細胞内シグナルについて詳細を明らかにしていくことで、創薬標的の拡大、ひいては新規治療薬の創出に繋げていけたらと考えています。
研究分野とは関係ありませんが、野球の大谷翔平選手が挙げられます。名前も似ていますし、何より不可能と思われていたことを可能にし続けている姿は、研究活動にも通ずる部分があり、その生き様や考え方から学ぶものが多いと感じます。
私が所属する研究室において、所属当初に直接ご指導をいただいていた野口先生には、研究の進め方からプレゼンテーションのコツまで、一から自分を育ててくださったので、大変感謝しています。
研究は楽しむことが第一だと思います。楽しいと思える範囲で、無理なく、研究に取り組みましょう。
所属
東北大学大学院 代謝制御薬学分野
名前
髙橋 建也
受賞タイトル
悪性脳腫瘍グリオブラストーマの予後改善を目指したセレン代謝阻害剤の開発
グリオブラストーマ(GBM)は最も悪性度の高い脳腫瘍であり、本研究では、GBMの悪性化に関わる因子であるセレノプロテインP(SeP)を抑制する化合物をスクリーニングにより発見し、この化合物のGBM細胞に対する増殖・遊走抑制効果やフェロトーシス感受性の向上作用を明らかにしました。また、脳腫瘍への薬物送達を実現するため、急速に脳に取り込まれることで知られるSePとその受容体ApoER2に着目した脳への新規輸送システムを考案し、その基礎を確認しました。
学部生からGBMについて研究を進めており、主に治療薬の検討を行ってきました。現在は脳への新規送達方法の開発にも力を入れています。
きっかけはセレンをはじめとした金属や毒性の研究を行っている研究室への配属です。
始めは毒性の発現メカニズムなどの理解に苦戦し頭を悩ませることが多かったですが、段々と色々なことを理解できるようになってきており、考察することが楽しいと感じています。
予想した結果と正反対の結果が出た時に要因を考察するのは大変でしたが、それと同時に面白い結果だと思いました。
脳腫瘍の研究を行っていく中で、実際の臨床現場や患者の声についても興味が湧いています。
「人間万事塞翁が馬」です。研究においても人生においても大事な考え方だと思っています。
研究室の皆さんに感謝していますが、特にお世話になっている外山先生に感謝したいです。日頃の懇切丁寧な指導のおかげで受賞できたと思っています。
優秀な後輩たちがいることはとても良い刺激になっています。抜かされないように頑張ります。
所属
広島大学大学院 医系科学研究科 生体機能分子動態学研究室
名前
佐藤 秀亮
受賞タイトル
香害の発症における脳内チトクロームP450の役割についての解明
香害は香水や柔軟剤などに曝露されることで生じる化学物質過敏症の一種です。その発症メカニズムを明らかにするため、代表的な香料成分であるリナロールを用いて動物実験を行いました。その結果、リナロールとその代謝物が脳内に蓄積し、嗅覚非依存的に香害様の症状を誘発することを発見しました。更に、薬物代謝酵素チトクロームP450の働きを阻害すると代謝物産生が抑制され症状が消失したことから、病態形成にとってそれらが重要であることが示唆されました。
修士課程までは、皮膚感作性物質によるアレルギー性接触皮膚炎の発症メカニズムを研究していました。博士課程に進学してからは、現在の香害に関する研究に取り組んでいます。
学部生の頃、アレルギーに関する研究に取り組みたいと思い、免疫毒性物質に関する研究テーマに従事したことが毒性研究を始めたきっかけでした。
研究を始めた当初は毒性研究がどの様なものか全く分からなかったので、深く考えるよりも先ずクリーンベンチに向かい手を動かす毎日でした。作業自体が目新しく楽しかったことを覚えています。最近は少しずつ研究への理解が深まり、毒性メカニズムを想像しながら実験方針や課題の解決策を思案する面白みが分かってきました。その分悩むことも多くなりましたが、これも研究の醍醐味を味わえるようになってきた証拠かなと、嬉しく思っています。
私の研究では、香料成分の影響を評価するためにマウスの行動を観察します。マウスは実験環境の些細な変化にも敏感で、思いもよらない要因によって行動が変化します。実験の度に様々な環境条件に注意を払い、マウスを丁寧に扱わなければ正確かつ再現性の良い評価は行えません。気にかける要素が多く大変に感じる一方で、神経を尖らせて観察する分マウスへの理解が深まる点は、非常に面白く感じています。最近ではマウスの顔色が何となく分かるようになりました。
アトピー性皮膚炎などアレルギー疾患に関する話題に以前から変わらず興味を持っています。いつか自らの研究テーマに出来れば嬉しいです。
私が今日も研究を続けていられるのは、研究活動を理解し支えてくれる父と、日々の生活や健康を気遣ってくれる母のお陰です。特に母の献身があったからこそ研究を続けてこられました。遠方に暮らす今も心配をかけていると思うので、今回良い報告が出来て嬉しい限りです。また、いつも気持ちを明るくしてくれる友人達も私の支えです。研究が苦しい時、彼らに元気をもらっています。普段伝えられない彼らへの感謝をこの場を借りて申し上げます。
麻布大学の関本先生、卒業後も気にかけて下さり有難うございます。先生のラボで過ごした時間が楽しかったからこそ、今も研究を続けています。また今度お会いしたら研究のお話をさせて下さい。その時により深いディスカッションが出来るよう、これからも精進します。
自身にも言い聞かせたいことですが、何事にも萎縮せず挑戦的でいて下さい。研究をしていると、自分の考えに自信が持てず二の足を踏む場面がたくさんあります。もっと調べてから、様子を見てからと悩んでいるうちに挑戦する機会は無くなってしまいます。失敗しても次に活かせる経験になりますし、やってみなければ分からない事がたくさんあります。迷ったときは思い切って取り組んで下さい。
所属
大阪大学大学院薬学研究科 分子生物学分野
名前
仝 嫣然
受賞タイトル
胆汁うっ滞型肝毒性の予測を目指した肝臓オルガノイド由来肝細胞の培養条件の最適化
前臨床試験で広く用いられるヒト初代肝細胞は、ロット間差、供給量の制限、培養に伴う肝機能の低下などの課題を有しており、肝毒性の予測の精度に欠けます。これらの課題を克服するため、我々は肝臓オルガノイド由来肝細胞を開発しました。しかし、現行の培養条件では胆汁うっ滞型肝毒性の予測に限界がありました。そこで本研究では、胆汁うっ滞型肝毒性の予測に資するin vitro評価系の構築を目指し、毛細胆管構造を有する肝臓オルガノイド由来肝細胞の創出に取り組みました。培養条件の最適化により得られた新規肝細胞は、十分な肝機能を示すとともに、胆汁うっ滞型肝毒性の予測に有用である可能性を示しました。
肝臓オルガノイドを用いた肝細胞モデルの作製に取り組んでおり、その創薬研究や再生医療への応用を目指して研究を進めています。
所属研究室が有する「肝臓オルガノイド」の技術が、医薬品開発における肝毒性予測の評価系として有用な肝細胞モデルとして注目されていることを受けて、毒性研究に取り組み始めました。
毒性研究を始めた当初は、被験薬による毒性の有無を判断する比較的シンプルな分野だと捉えていました。研究を進める中で、毒性の発現には多様なメカニズムが複雑に関与していることを学び、体系的な理解の重要性を痛感しています。
実験結果が仮説と異なったとき、その理由を考察する過程に、研究の醍醐味を感じます。現象の背後にあるメカニズムを解明するには、多くの時間と労力を要しますが、得られる予期せぬ発見が、何よりも研究のやりがいにつながっています。
現在は、AIを活用した創薬スクリーニングに興味を持っています。AI技術の進展と普及に伴い、毒性研究の在り方も変化しているため、常に最新の知見を取り入れながら研究を進めていくことが重要だと感じています。将来的には、これまで培ってきた知識と経験を活かし、安全かつ効果的な医薬品の開発を通じて、人類の健康の向上に貢献したいです。
「人事を尽くして天命を待つ」です。どのような結果が訪れようとも後悔のないよう、日々全力を尽くすことを心掛けています。
これまでの研究活動を通じて多くの学びと成長の機会を与えてくださった水口裕之先生に、心より感謝申し上げます。今後ともご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
何よりも健康を大切にしながら、一歩ずつ着実に進んでいきましょう。
所属
岡山理科大学大学院理工学研究科 自然科学専攻生命科学コース
名前
日笠 理公
受賞タイトル
間葉系細胞の多細胞凝集塊を組織床としたin vitro汗腺導管の出芽形成誘導
現在までに、汗腺の細長い導管様構造体の形成を培養下で誘導した報告はほとんどありませんでした。本研究では、生体汗腺の周囲環境を模倣した間葉系細胞の凝集塊中で汗腺細胞を培養することで、初めて培養環境下にて導管様構造体を細胞凝集塊から出芽するようにして形成させることに成功しました。医薬化粧品の薬効毒性の評価や研究モデルへの応用を目指して、さらなる研究開発を進めております。
岡山理科大学フロンティア理工学研究所の動物細胞工学研究室に所属し、4年次には再生医療用の立体気管軟骨の作製に関する研究を通じて組織工学技術の基礎を学びました。博士前期課程からは、新たに汗腺組織の作製と毒性評価に関する研究に取り組み始め、1年半が経過し現在に至ります。
組織工学技術を駆使して立体的な3次元組織体を作製できれば、再生医療のみならず薬物の毒性評価や研究モデルとして有用であると考えたからです。薬物が組織の3次元構造に及ぼす影響を培養で正確かつ詳細に評価できるようにしたいと考えております。
最初は、とにかく生体汗腺を模倣した組織が作製できればそれで良いと考えておりました。しかしながら、再生医療用の組織とは異なり、毒性研究に用いる組織は評価のしやすさも求められると現在は感じております。例えば、顕微鏡で観察可能なサイズや、観察しやすいように位置固定化された状態で組織を作製する必要があると考えております。
まだ研究を始めて2年足らずですので、日々新しい挑戦ができて面白いことばかりです。特に、この度の研究成果が得られた時は、(部分的ではありますが)世界で誰も見たことがない汗腺導管様組織の培養下での形成を私が初めて見ることができている、と思って大変ワクワクしました。
まさに現在行っている研究にて恐縮ですが、生体組織の3次元構造を模倣した培養モデルで、薬物に対する組織の3次元構造の変化を捉えることができるのか!?ということに今は最も興味を持っております。将来的には、毒性研究をはじめ薬効評価や組織再生にも有用な生体模倣組織体の開発を行う組織工学者として社会貢献したいと考えております。
正範語録です。特に、「判断力の差は情報量の差」という一節は研究する日々の中で毎日心に刺さります。次の一手を打つために、多くの論文や専門書を日々読み情報収集する必要があると思います。毎日意識するように、研究デスクに貼っております(笑)。
この度、このような大変栄誉な賞を受賞することができ、指導教員である岡山理科大学フロンティア理工学研究所の岩井良輔 准教授に心から感謝申し上げます。培養汗腺導管様組織の毒性研究への応用に向けて頑張りますので、引き続きご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い致します!
工学的視点からも毒性研究の発展に役立つ研究が沢山あると思います。自分の強み(専門)を分野の垣根を超えて活かしていきましょう。
所属
富山大学 研究推進機構 研究推進総合支援センター 生命科学先端研究支援ユニット 分子・構造解析施設
富山大学 学術研究部 薬学・和漢系 ゲノム機能解析研究室
名前
平野 哲史
受賞タイトル
フィプロニル代謝物が引き起こすミクログリア-ニューロン間相互作用の撹乱メカニズムの解明
本研究では、化学物質曝露によりミクログリアが活性化した際にどのようにニューロンとの細胞間相互作用が撹乱されるのかを明らかにすることを目的としました。フェニルピラゾール系農薬フィプロニルの主要代謝物であるフィプロニルスルホン(FipS)を曝露すると、ミトコンドリア機能の低下に伴ってミクログリアの活性化がみられ、さらにミクログリア由来エクソソームに含まれるいくつかのmicroRNAがニューロンの突起伸長を正に制御することを明らかにすることができました。本研究の成果は、ミクログリアの活性化が関与する新たな神経毒性の上流メカニズムの一端を示すことができたのではないかと考えています。
学部から大学院にかけては神戸大学の農学部、農学研究科にて応用動物学を専攻し、種々のストレスに対する個体レベルの応答に興味をもって研究を始めました。現在は富山大学のゲノム機能解析学研究室にて、さらに研究対象を細胞レベルのストレス応答メカニズムにも広げて研究を続けています。
研究室に配属後、研究テーマを決定するにあたって指導教官の先生とディスカッションを重ねるうちに、「目に見えない」化学物質やストレスが私たちの身体にいかに作用しているかについて、実験により「目に見える」形で明らかにできるところに面白さを感じたのがきっかけです。
研究を始めた当初は、既に世に出ている化学物質の毒性影響を調べることに後ろ向きなイメージを持っていたように思いますが、現在は未来を守ることに繋がるポジティブな仕事であると捉え、やりがいを感じるようになりました。また、基礎科学と応用科学、両方の側面を持っている上、医学、獣医学、薬学、農学等さまざまな領域が関連する点で興味深いと感じています。
これまでに新たな実験系や手法の立ち上げを多数経験しましたが、論文通りにやって上手くいかないことの方が多く、途方に暮れることが何度もありました。一方で、条件等を工夫しながら上手くいくまで試行錯誤しているプロセスを最も面白いと感じています。
オミクス解析とバイオマーカーを毒性研究においてどのように活用するかに興味を持っています。また、いつかは自身のラボを持って独自の成果を発信できるようになりたいと思っています。
子供のころに何かのテレビで見た「一生の最もすぐれた使い方は、それより長く残るもののために費やすことだ。(ウィリアム・ジェームズ)」という名言に感銘を受けたので座右の銘にしています。研究成果を論文として発表することや学生さんの教育に携わる際のモチベーションに繋がっています。
神戸大学大学院 農学研究科の星 信彦教授には、学生時代から研究に必要なあらゆる要素をご教授いただき、またプライベートに関してもたくさん相談に乗っていただき本当に感謝しております。まだまだ至らぬ点ばかりですが、先生のような研究者になれるよう今後も努力していきますのでよろしくお願いいたします。
研究には大変なことだらけだと思いますが、行き詰ったときにこそ、一歩下がって広い視野や別の見方をもって臨んでほしいと思います。また、このような研究の経験はどのような分野であっても役に立つと思いますので、限られた時間を有意義に使って楽しんでいただけたらと思います。
所属
九州大学大学院薬学研究院 薬物動態学分野
名前
福田 大輝
受賞タイトル
マクロファージおよび概日時計機構に着目したバンコマイシン誘発性腎障害の発症機構解析
MRSA治療薬であるバンコマイシン(VCM)は急性腎障害を頻発し、臨床上重大な問題である。また様々な薬物の副作用の発現が、投与時刻によって変動することが知られている。そこで本研究では、この投与時刻に基づいた時間薬理学的観点からVCM腎障害の発症機構を解析した。その結果、マウスの休息期である午前9時にVCMを尾静脈より投与すると腎障害が増悪し、この投与時刻依存的な差異にマクロファージが関与していることが明らかになった。このことからマクロファージに着目した詳細な解析がVCM腎障害の発症機構の解明につながる可能性がある。
学部時代から大学院にかけて、上記のバンコマイシン誘発性腎障害の発症機構の解析を行っています。
学部時代に薬物の副作用の発現が投与時刻に応じて変化することを知り、より最適な薬物治療法の確立に貢献できるのではないかと考えるようになりました。
マウスへの投与実験で朝に投与したマウスと夜に投与したマウスで腎障害の発症に差異が生じることに驚きを感じました。腎障害を解析する上で腎臓は複雑な臓器であり、分子レベルの解析を行おうとすると解剖学や生化学などの数多くの専門知識を必要とし、自身の勉強不足や知識不足を痛感しています。
毒性研究に限った内容ではありませんが 、実験結果が仮説通りになることや反対の結果となることがあり、生命現象の面白さを感じています。投与時刻に基づいた研究であるため朝と夜で同様の実験を行うことになり、朝に開始し夕方までかかる実験を夜に開始するときは非常に大変でした。
腎障害の研究を行って、腎臓の複雑さや恒常性を保つための機能を学び、腎障害に数多くの要因が絡み合っていることを知り、それらを明らかにしていくことに興味をそそられます。
人間万事塞翁が馬
これまでの人生を陰から支えてくれた父親へ感謝を申し上げます。大学進学時に研究者を目指すことを信じて生活面などを支えていただきありがとうございます。まだ自分の目指す研究者像からはかけ離れていますが、より一層精進いたします。
研究を行っていく上で自身の意見や考えをしっかりと持つことと同時に、周りの人と双方向に技術や知識を補い合いながら遂行していくことが重要であると思います。
所属
静岡県立大学 薬学部 生体情報分子解析学分野
名前
清水 聡史
受賞タイトル
マルチオミクスによる腎臓近位尿細管におけるシスプラチン排泄機構の性差同定
本研究では腎臓における性差形成メカニズムの解明を目指して、膜タンパク質に特化したプロテオミクス・トランスクリプトミクスを行い、性染色体・性ホルモン由来の影響を分けて性差分子を同定しました。膜プロテオミクスはポスドク時代の研究室が開発した方法であり、解析が困難な膜タンパク質複合体を高感度で検出することができます。その結果シスプラチンの腎毒性の性差が高齢になると逆転することを含め、どのように起こるかを説明できる結果が得られました。
大学院生時代は心不全の発症・進展に関わる転写因子の詳細な活性化機構の研究を、ポスドク時代では主に腎臓の膜タンパク質の生化学実験・プロテオミクス等の網羅的解析を行っていました。現在の所属になってからは、性差をキーワードに心・腎の解析を行っています。
はっきりとした、きっかけは分かりません。現在行っている網羅的な解析は特性上、莫大な結果が得られます。その中から、何が明らかとなっているかを探り当てるときに、自分の背景にある「薬学」などが影響して毒性にも目を向けるようになったのだと思います。
毒性研究はまだ踏み入れたばかりですので、この業界では当たり前とされていることがわからなかったりします。先人の研究を調べて勉強をしていますが、実験系が今まで試したことがないものも多く、困惑しております。
毒性研究に限りませんが、今までわかっていなかったことが明らかになる瞬間は気分が高揚します。その結果を得るまでに試行錯誤する過程が大変でもあり、自分が面白いと思うところです。
今興味があるものはデータサイエンスです。科学技術の進歩により様々なデータで溢れかえっています。毒性研究に限りませんが、実験で得られたデータから後ろ向き研究を気軽に行ったり、オミクスデータをパッと活用できるようになりたいです。
「失敗は成功の母」です。エジソンも「失敗は積極的にしていきたい。なぜなら、それは成功と同じくらい貴重だからだ。失敗がなければ、何が最適なのかわからないだろう」と言っています。
多くの先生のおかげで現在の私がありますが、敢えて1人であればポスドク時代のボスである永森收志教授に、博士取得直後の小僧に研究者としての心構えから教えていただきこの場をお借りして感謝申し上げます。先生の名に恥じぬようにより一層研究に努めてまいります。これからもよろしくお願いいたします。
現在行っている分野だけに凝り固まらずに様々な分野に顔を出してみてください。他の分野の人との繋がりは刺激的ですし、自分の研究に必ず活きると思います。
所属
徳島文理大学 大学院薬学研究科 衛生化学分野
名前
田口 央基
受賞タイトル
シスプラチン耐性近位尿細管細胞を用いた新規シスプラチン腎障害責任因子の探索
本研究では、抗がん剤であるシスプラチン(CDDP)の副作用として知られる腎障害発症機構の解明を目指し、CDDPに耐性を獲得させた腎近位尿細管細胞を用いて検討を行いました。CDDP耐性細胞では、セレノプロテインP(SeP)が高発現しており、SePのノックダウンによりCDDP毒性が増強することから、CDDP腎障害にSePが関与している可能性が示されました。
学部生の頃から現在に至るまで、CDDPによる腎障害発症機構の解明を目指し、マウス近位尿細管S1,S2,S3領域由来不死化細胞などを用いた研究に取り組んでいます。
「金属化合物の生命科学研究」をテーマに研究を行っている衛生化学研究室に配属されたことがきっかけです。研究活動を通して、金属化合物による生体への毒性発現機構に興味を持つようになりました。
研究を開始した当初は、知識も技術もなかったので、所属研究室の先生たちが実験をする姿を見て「なんか面白そうだから自分もやってみよう!」と思い、研究を行っていました。現在では、所属研究室の先生方と議論を行い、研究を推進していくことで毒性研究の面白さを実感しています。
研究活動を通して、毒性研究が非常に奥深いものであると感じています。今後、研究を行っていく上で、金属化合物の毒性研究だけではなく、他分野の知識を学ぶ必要があると強く実感しています。これから、様々な知識や技術を吸収し、応用することで自身の研究に活かせるよう精進してまいります。
将来は薬学部の教員として、研究と教育に携わりたいです。研究者としては、金属化合物(毒物)の作用機序を応用することで医薬品の開発につなげるような研究(毒性学と創薬学の複合研究)に取り組みたいです。
配属当初より、研究を自由に行える環境を整え、支えてくださっている所属研究室の先生方に心より感謝しています。また、本受賞研究に関して研究のアドバイスや貴重な研究試薬を快く提供してくださった東北大学の斎藤芳郎先生、外山喬士先生にこの場をお借りして感謝申し上げます。
前教授である姫野誠一郎先生にこの場をお借りして感謝申し上げます。姫野先生の学生目線で最後まで見放さず学生を指導する姿勢や楽しそうに講義や研究に取り組む姿を見て、自分も姫野先生のような大学教員になりたいと考えるようになりました。今後ともご迷惑をかけることが多々あると思いますが、ご指導の程よろしくお願いします。
研究活動から得られる問題に対して臆さず立ち向かう力や解決するために自ら考える力は、薬剤師として医療現場で働く際に非常に重要になってくると思います。これからも、共に研鑽に励みましょう。
所属
中外製薬株式会社TR本部安全性バイオサイエンス研究部
名前
山室 友紀
受賞タイトル
In vitro血管局所刺激性評価系の構築とその有用性
静脈内投与の薬剤における溶媒の局所刺激性をin vitroで評価する系を構築しました。溶媒添加によるヒト臍帯静脈内皮細胞の経内皮電気抵抗値(TEER)の低下率を評価し、ATPによる生細胞率評価では検知できなかった弊社in vivo 試験使用溶媒の局所刺激性を検知できました。難溶性の化合物が増加し使用実績のない溶媒を使用せざるを得ない状況が起こりうる中、本系をスクリーニングとして使用できればと思っています。
獣医学科の生理学研究室に所属しエストロゲンと腸内細菌叢の関係を調べるために卵巣摘出マウスで行動解析や腸内細菌叢解析をしていました。その後テーマを変えてLAO1とホモログ遺伝子であるIL4ilの両遺伝子欠損マウスにおける乾癬病態の解析を行い、IL4i1の炎症における機能探索を行いました。
入社後一般毒性を評価する部署に配属となり毒性評価を学び始めました。
入社当時は生物学的な学びにしか興味がありませんでした。現在5年目で毒性機序の解明がモチベーションであることは変わりませんが、ガイドラインで定められた事項も合わせた統合的な評価を行うことも化合物の開発に重要であることを知り、両面を理解している人物になりたいと考えています。
毒性評価の中で面白いと感じるのは種差です。多くの化合物の毒性試験は2種の動物で実施するため、毒性の表現型に種差が見られることがあります。よりヒトへの外挿性が高いのはどの種なのか(どの種でもないのか)を考えるのは難しいですが興味深いです。入社してすぐにある化合物によるラットでの肝肥大のヒト外挿性をin vitroで評価する仕事をしましたが、ラットとヒトの種差を示すための系構築やその機序の検討は楽しかったです。
今興味を持っているのは薬物動態です。毒性評価の中で動態への理解は重要と思うようになり勉強しています。同じ研究所に動態の専門家がいるので質問もしやすく製薬企業の強みを感じています。
将来は毒性評価をしっかりと行いメッセージとして伝えられるようなin vivo試験責任者になりたいと思っています。またin vivoを主軸に置きつつも今回発表した内容のようにin vitroの系も構築できるような人材になりたいです。
座右の銘はないですが、業務の中で自分の考えを広げられる場所がないかは積極的に探すようにしています。そういう姿勢は研究室の教授と同期から学んだと思います。
入社し分からないことばかりの私にOJTコーチとしていつも親切にご指導くださった現グループマネージャーには本発表においても非常にお世話になりましたので、この場でお礼を申し上げます。
自身もまだまだ未熟で後輩にサポートされてばかりですが、少し経験を積んでいる部分で後輩をサポートできることがあれば嬉しいです。先輩後輩関係なく多様な専門性を持ったメンバーで議論できるような場を作っていきたいと思います。
所属
第一三共株式会社 安全性研究所
名前
紺野 紘矢
受賞タイトル
AIを用いたカニクイザルにおける異常行動検出モデルの構築
深層学習等を活用し動画データからサルの異常行動を自動解析するモデル構築を試みました。カニクイザルの骨格推定モデルを活用し異なるアルゴリズムを用いた教師あり学習により、カニクイザルにおける4種の異常行動(活動量低下、常同行動、嘔吐、痙攣)の各検出モデルを構築しました。これらのモデルにより、各行動の発生タイミングの検出及び定量的な評価が可能となりました。これらの新たな指標により、毒性評価の精度向上だけでなく、異常行動の早期検出による獣医学的ケアや飼育環境の最適化への応用が期待されます。
顧みられない熱帯病の一つであるリーシュマニア症のうち、内臓リーシュマニア症を引き起こすLeishmania donovaniについて研究していました。L. donovaniでは、ヒトへの感染経路の重要な役割を担う保虫宿主が明らかとなっていませんでした。そこで、イヌにL. donovaniを投与し、長期的に感染が確認されるかを検証することで、他のLeishmaniaと同様L. donovaniにおいてもイヌが保虫宿主である可能性を明らかにしました。
大学時代から毒性学の授業は受けておりましたが、毒性研究を始めたきっかけは当社への入社です。
入社当初は正常を知ることから始めましたが、その重要性を理解できていなかったと思います。私が日頃研究対象としてるイヌやサルでは個体差が特に大きく、正常/異常を判断することが困難であると同時に重要になります。正常に対する理解が深まり、毒性評価の経験が増えてきた近年では異常について適切な判断・解釈ができるようになってきたと思います。
面白さは仮説に沿った結果が明確に出たときだと思います。一方で、綺麗に仮説にはまりすぎているとむしろ心配になってしまうところも研究の醍醐味なのかもしれません。また、大変さは、やり直しが許されないケースが特にin vivo研究では多々存在する点だと思います。
これまでin vivo毒性評価で焦点を当てづらかった分野に興味を抱いております。例えば、今回の行動評価もその評価の難しさ(複雑性・主観的・労力の大きさなど)から、いまだ十分に確立したとは言い難い分野の一つだと思っています。また、毒性試験で多く認められる個体差についても、様々な要因が存在するため明確な答えを出すことが難しく、原因の追究については進んでいない分野だと感じており、現在遺伝子多型などの観点から研究を行っております。
1日1つ何か成長したと実感できることをするように心がけております。
研究の面白さをお教えくださった北海道大学獣医学部 寄生虫学教室 前教授 片倉賢先生 にこの場を借りて、厚く御礼申し上げます。
先生との出会いが無ければ、今頃北海道の大地で牛と戯れていたことと思います。
大変優秀な後輩たちのおかげで日々とても良い刺激をいただいております。
お手柔らかにこれからも宜しくお願い致します。
所属
国立医薬品食品衛生研究所 病理部
名前
山上 洋平
受賞タイトル
アセトアミドのラット肝発がん過程における染色体再構成の関与の検討
小核とは、通常の核とは別に細胞中に存在する小型の核であり、染色体異常の指標として使用されてきましたが、小核そのものについてはあまり注目されていませんでした。本研究では、アセトアミドによって誘発した肝腫瘍を解析することで、小核形成を介した染色体の再構成により染色体外DNA(ecDNA)が生じ、その結果生じるがん遺伝子の増幅が、アセトアミドの肝発がん過程に関与している可能性を明らかにしました。
抗がん剤が誘発する間質性肺炎のメカニズム解析に関して、上皮細胞から間葉系様の形質へと変化する現象である上皮間葉転換に着目し研究しておりました。
学生時代に配属された研究室が医薬品の副作用誘発メカニズム解析を行っていたのがきっかけです。
有機や薬理の研究と比較すると、地味な研究だと感じたのが第一印象です。他分野の研究成果報告を聞いた際に、きらきらしたデータを羨ましく思ったのを覚えています。一方現在は、毒性研究の面白さや奥深さを感じており、日々の学びが多いため、非常にやりがいのある研究分野であると思っています。
データの再現性が取れないときや、想定通りの結果が得られないことが続くと大変ですが、一つのブレイクスルーで一気に研究が進捗するときは、研究の面白みを感じます。
現在は、毒性学全般に興味を持っております。毒性研究を進める上では、幅広い知識と経験が必要であると感じており、今後も研究や勉学(認定トキシコロジストの取得など)を通して、知識・経験を養っていきたいです。そして、将来は毒性研究者として活躍できる人材になりたいと考えています。
七転び八起き
うまく進まないときでも、めげずに、粘り強く研究を続けていきたいと考えています。
現在指導いただいている国立衛研 病理部の石井先生には感謝の念に堪えません。先生と議論する中で、実験データに対する考察力を鍛えることが出来ていると感じています。私は以前よりオーバーディスカッションをしてしまう癖がありますが、その癖も抜けつつあり、データや論文報告に基づいた考察が出来るようになってきました。色々と至らぬ点もありますが、引き続きご指導のほどよろしくお願い致します。
研究は、上手くいくことの方が少ないですが、粘り強く挑み続けてほしいを思います。また、周りの研究者とのつながりを大切に、楽しく研究生活を送ってください。
所属
中外製薬株式会社 トランスレーショナルリサーチ本部 安全性バイオサイエンス研究部
名前
須藤 優喜
受賞タイトル
ヒト腸管オルガノイドを用いた消化管毒性評価系の構築
ヒト腸管オルガノイドと画像解析を用いて消化管毒性評価系の構築を行いました。消化管毒性を引き起こす化合物を処置するとオルガノイドのサイズが減少することから、サイズ定量により毒性評価を行うことを考えました。その結果、画像解析のためのアプリケーションを開発し、より簡便に消化管毒性を評価することに成功しました。
大学院ではアルツハイマー病とアストロサイトの関係性についての研究をしていました。アストロサイトは中枢神経系の機能維持に重要な役割を担っている細胞です。アルツハイマー病の原因タンパク質を分解するプロテアーゼをアストロサイトが分泌することから、その分子の発現制御機構の解明を目指していました。
入社し、安全性研究部に配属されたことがきっかけです。学生時代には毒性研究というものになじみがありませんでしたが、現在では薬が与える生体反応を毒性という観点から研究でき、やりがいを感じています。
安全性研究というと化合物を動物に投与して毒性を見る、ということを思い浮かべていましたが、実際に入社後はin vitroをメインとした研究をしています。単に毒性を見るだけでなく、毒性メカニズムの解明など幅広い研究を行えることができ、毒性学の幅広さを感じています。
非臨床研究を通じてヒトでの毒性を予測するには?ということを日々考えて研究することです。製薬企業の安全性研究として究極の課題だと思いますが、少しでもヒト予測に近づけるように努力しています。
毒性研究を通じて新しい薬の創製に貢献するとともに、生物学への新しい知見についても明らかにできるような毒性研究者になりたいと考えています。まずは現在の消化管毒性の評価系を用いた研究を一生懸命に行い、自身の研究基盤を構築できればと考えています。
日々周りの方に大きく支えてもらって今の自分があると思っています。周りからのサポートを忘れることなく、精進していけたらと考えています。
社内の方々へ、毒性研究を全く知らなかった自分に対し、いろいろと教えていただいてありがとうございます。早く一人前になり研究を通じて皆様に恩返しできるように頑張ります。
私自身も毒性研究者としてはまだまだ未熟ではありますが、ともに毒性研究を楽しみ、盛り上げていきましょう。
所属
千葉大学 予防薬学研究室
名前
福田 彩乃
受賞タイトル
メタボローム解析によるヒト肝がん細胞(HepG2)における低温ストレス応答機構の解明
低体温を模倣した低温条件において、ヒト肝がん細胞であるHepG2の応答メカニズムを解明しました。細胞が低温条件下にさらされると、細胞内にカルシウムが流入しタウリン量が増加し、最終的に抗酸化機構が活性化されることを明らかにしました。
受賞研究を進めています。主にHepG2を培養して実験を行い、測定ではLC-ESI-MSやLC-ICP-MSを用いています。
学部時代に、今所属している研究室に入ったからです。安全性や毒性に興味があり、そういった分野の研究を行っている研究室を選びました。
研究を始めたときは、初めて触れる実験手技や専門用語が多く研究室生活に慣れることが大変で、ストレスが多い日々でした。現在は、研究成果がでてきて学会に参加させていただく機会も増え、忙しいですが充実した日々を送っています。
細胞を使った毒性研究で大変なことは、細胞の調子によって結果が変わることがあることです。細胞も私たちと同じように調子がいいときと悪いときがありますが、増殖具合などからしか感じることができないため、判断が難しいです。
企業の研究職に就き、研究を通して人の役に立ちたいです。
研究に限らず日々の生活で、「やらぬ後悔よりやる後悔」という言葉を大切にしています。研究では、手を動かして実験をやってみることで見えてくることが多くあると思うからです。
日々熱心にご指導くださる予防薬学研究室の小椋康光教授をはじめとする先生方に心から感謝申し上げます。日々のディスカッションや研究環境が私の研究を形にしてくれて、今回の受賞につながったと思います。
私が研究室に通うことができているのは、良好な人間関係もあると思います。明るく楽しい研究室を作ってくれている先輩や後輩に感謝します。
所属
九州大学大学院薬学研究院薬物動態学分野
名前
福岡 航平
受賞タイトル
ビタミンA蓄積を介した腸管IgA分泌異常によるCKD性心筋症増悪機構の解析
慢性腎臓病は様々な合併症をもたらし、有効な治療法の乏しい世界的な健康問題です。今回我々は慢性腎臓病(CKD) モデルである5/6腎摘出マウスを用いて、CKD時に血中に蓄積する“ビタミンA”が腸内細菌の乱れを引き起こすという「腎-腸連関機構」を発見しました。具体的にはCKD時において腸管免疫分子である免疫グロブリンAの産生に異常が生じ、これが尿毒症物質の蓄積をもたらすことを明らかにしました。
主に (急性/慢性) 腎臓病時において、他の臓器の機能にどのような変化をもたらすかを明らかにするため、特に免疫細胞に着目した解析を行っております。
腎臓病患者では種々の物質の血中濃度が上昇します。私は健康な時には体に有益であるが、蓄積すると毒性を示すというビタミンAの二面性に強い興味を持ち、毒性研究に足を踏み入れました。
毒性学というと何か特定の毒性物質の機能を研究する学問であると思い込んでいましたが、実際には疾患の増悪経路や毒性を評価する手法の研究など、生物学と切っても切れない幅広い研究分野を担う重要な学問であることに気づきました。
私は腸内細菌叢を取り扱う研究を行っております。同じCKDモデルマウスでも飼育環境や季節に応じて、異なる細菌叢を示すことが研究の大変なところであり興味深いところです。
私は現在病態時の分子生物学的解析研究を実際に医薬品として昇華することを目指して、構造情報を基盤とした創薬を行うための「構造解析学」と「化合物ドッキング」を習得中です。
『神様のカルテ』より「学問を行うのに必要なものは、気概であって学歴ではない」という言葉を座右の銘として挙げさせていただきます。どのような立場になっても、新しい発見をした時の喜びと研究に対する熱意を持ち続けていたいものです。
これまでご指導いただいた先生方へ:研究において多方面からのご指導を賜り、心より感謝申し上げます。まだまだ未熟な点も多いですが、先生方のような優れた研究者を目指し、今後も一層努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。なお、これまでご指導いただいた先生方に恵まれてきたため、恩師を一人に絞ることはできませんでした。素晴らしい先生方との巡り合わせに、改めて感謝申し上げます。
締切に追われて夜遅くまで作業することも多いかと思いますが、質の良い睡眠はパフォーマンス向上に欠かせません。しっかり休んで、健康を大切にしてくださいね。
所属
東京大学大学院 農学生命科学研究科 獣医衛生学研究室
名前
永嶋 祐安
受賞タイトル
中枢神経系に対する安全性薬理試験評価法としての心拍変動解析の有用性に関する研究
安全性薬理試験において薬剤への中枢神経系への影響を評価するために、心拍変動解析が有効活用できないか、ということについて検討を行いました。結果としては、投薬後のLF/HFの最大変化量が薬剤の中枢神経に対する作用を反映していたのではないかと示唆されました。
乳幼児突然死亡症候群という症候群について研究しています。具体的には、リスク因子の一つと考えられている周産期のニコチンの曝露が子どもの神経発達に与える影響を電気生理学、分子生物化学などの手法を用いて評価しています。毒性学の中では発達神経毒性にあたるのかと考えています。今回受賞したテーマは他の研究室員から引き継いだサブプロジェクトに当たりますが、学ぶ点も多かったです。
学部生時代の研究です。もともとは呼吸や循環制御といった生命維持に必須である生理機構に興味があったため、心毒性を持つ薬物に関する研究を行いました。その中で毒性学の面白さに触れ、現在に至ります。
本質を掴むのが難しい、というのが最初の印象です。ある単一のメカニズムだけでは説明できないような現象を対象にするので幅広い知識が必要であり、学部生の自分はとにかくデータを出すことしか考えられませんでした。ただそれが面白い点でもあり、如何にしてデータに意味をもたせ、曖昧に見えてしまう研究対象を具体化し考察していくか、という深さのある学問領域であるという印象を今では持っています。
データ解析の過程で予想とは異なる結果となった場合、そもそも予想が間違いなのか、解析方法が違うのか、データの取得方法がよくなかったのか、など考察することは大変ではあるのですが研究における面白い点だと考えています。
如何に動物から得られるデータを最大化し、ヒトへの影響を予測するのかということに興味があります。将来的には、もう少しヒトのデータも扱いたいなあとも考えているのですが、まだ目の前の研究に必死ですので研究者としての成長が必要だと考えています。
誰かの言葉ではないのですが「人生のあらゆる事象は運に依存する」ことを常に胸に留めています。運任せにならないように、できるだけ多くのチャレンジをして、一喜一憂せず、チャンスをものにするために日々過ごしています。
ご指導していただいている関澤信一先生にこの場を借りて感謝申し上げます。先生のご助力無くして受賞はなかったと考えています。しかしながら私は未だ至らぬところばかりですので、今後ともよろしくお願いいたします。
全体を俯瞰しながら一歩ずつ進むことができれば、大体なんでも実現できるはずです。ともに精進しましょう。
所属
東北大学大学院薬学研究科 代謝制御薬学分野
名前
髙島 隼人
受賞タイトル
炎症に伴い誘導される一酸化窒素によるセレン代謝リモデリング機構
今回我々は、マクロファージの炎症性状態への分極時にセレンの利用が抑制され、グルタチオンペルオキシダーゼ (GPx) をはじめとしたセレノプロテインの発現が低下することを発見しました。さらに、このセレン利用抑制には分極時に誘導される一酸化窒素によるセレン代謝酵素のニトロシル化が関与すること、一酸化窒素はマクロファージのみならず周辺臓器でのセレン利用をも抑制することを見出しました。
特にセレンの代謝に焦点を当てて研究しています。現在は、親電子物質によるセレンの代謝かく乱メカニズムとその意義についての研究を進めています。
現在の研究室に配属され、セレンというマイナーですがとても興味深い分野に出会えたことがきっかけです。
研究を始めたばかりのころは (今でも怪しいですが) 全然知識がなかったので、とりあえずやってみよう、で研究をしていました。現在は、少しずつですが自分で展望を考えることもできるようになり、研究の楽しさを感じています。
自分の立てた仮説と実際に得られたデータの乖離が大きいと不安になることもありますが、そこから思いがけない知見が得られたときに毒性研究の深さ、面白さを感じています。
セレンという元素について、今はまだ知らないことばかりですが、これからもっと深く知っていけたらと思っています。
斎藤芳郎教授をはじめとした、所属研究室の先生方に日々支えていただいています。先生方との出会いが研究者としての道を考えるきっかけになったので、大変感謝しています。
指導教員である外山喬士先生に心から感謝しています。至らないところばかりの私ですが、日々熱心にご指導いただいているおかげで何とかやれています。また、私が研究の面白さに気づくことができたのは、楽しそうに研究を行っている先生の姿があったからです。まだまだご迷惑をおかけすることが多いかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。
研究室の後輩たちは賑やかで、いつも元気をもらっています。皆さんのおかげで毎日楽しく研究ができています。これからも明るく楽しい皆さんでいてください。
所属
山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部 衛生化学分野
名前
藤村 沙季
受賞タイトル
子宮内血流不全が脳発達に及ぼす影響:発達神経毒性の横断的理解
様々な環境汚染物質の妊娠期曝露は、共通した病態として、胎児への血流異常を引き起こします。そこで、胎児への血流不全そのものが胎児の脳発達に及ぼす影響を分析しています。本研究では、子宮内血流不全モデルラットを用いて、脳神経細胞の構成バランスを経時的に解析した結果、胎児期における血流不全が、GABA作動性介在神経の成熟を遅延させることを明らかにしました。この神経細胞構成の乱れは自閉スペクトラム症などの神経発達症との関連が示唆されています。
所属研究室では、環境汚染物質による脳発達への影響をテーマに研究をしております。子宮内低灌流を再現した新しい動物モデルを用いてフローサイトメトリーで解析を行っており、神経発達異常の早期予測因子の発見や発症予防の確立を目指して研究に取り組んでいます。
研究室配属の際に新生児の健全な発育の実現に興味をもっており、神経発達障害について調査していく中で、子宮内の血流不全やその血流不全に伴う低酸素低栄養状態が基盤病態にあることを知りました。その要因の一つとして環境汚染物質があり、毒性研究にたどり着いたのがきっかけです。
毒性学は研究を行うほど、あらゆる学問分野や社会の仕組みに関わってくることを実感し、毒性学の持つ役割やその研究を行う意義の複雑さと奥深さを実感しています。
動物実験ならではの地道な作業や個体差の影響、解析では条件検討など様々な工程で試行錯誤が必要でした。やりがいもあり研究ならではの大変さもありました。
今回発表した際に多くの方と直接議論して意見を頂いたため、より神経生理学に興味を持ちました。来年から病院薬剤師として勤めますので、この毒性研究を通じて得た多面的な考え方や幅広い知識を医療現場に役立て、将来的に新生児医療に関わりたいと考えております。
「継続は力なり」です。何事においても壁がありますが、努力を惜しまず継続することで大きな成果に繋がると信じています。
研究に対する姿勢や研究の面白さを知ることができ、楽しく研究を行うことができています。日頃から親身になってご指導くださる先生方に感謝申し上げます。また、この機会に水炊きをご馳走になりありがとうございました。
研究で思い通りにならないときでも、そこから学べることやアイデアが浮かぶことは多々あると実感しています。周囲の同期をはじめ先輩後輩などとたくさんコミュニケーションを取ることでより充実した研究生活になると思います。
所属
岐阜薬科大学 衛生学研究室
名前
長平 萌花
受賞タイトル
母体免疫活性化による神経発達影響評価における神経分化トレーサーマウスの有用性検証
現在、妊娠期の化学物質曝露等に起因する母体免疫活性化が、児の脳発達に与える影響が懸念されていますが、その評価においては研究に要する時間・労力・実験動物の数が課題となっています。本研究では、当研究室で樹立した神経分化トレーサーマウスが、母体免疫活性化による児の脳発達に与える影響を経時的かつ簡便に評価できる新規評価系として有用である可能性を明らかにしました。
妊娠期の内外的要因が児の脳発達に与える影響を上記のマウスを用いて検証しています。
きっかけは、当研究室の教授である中西 剛先生のResearch mapです。研究室選択の際に、多くの教授のResearch mapを拝見する中で、中西先生の毒性学というキーワードに「毒性学!なんだかカッコいい!」と感じて、毒性学を専門とする当研究室への所属を決めて研究を始めました(笑)。
自身の研究テーマに関して、研究を始める前は「既知な気がするな…。」と、感じていました。しかし、文献調査を進めていくにつれて、既知だと思い込んでいた多くの現象が意外と解明されていない事実に衝撃を受けました。現在は身近で未解明な現象だからこそ、研究を進めていくことに楽しさを感じています。
文献を参考に独自の手法で検討を重ねた結果、新たな現象に辿り着いた瞬間が最高に面白いと感じます。一方、実験結果が自身の立てた仮説とは相反するものであった際には考察に大変苦労したことに加え、自身の無力さを痛感して研究は大変なものだと感じました。
認定トキシコロジストの資格取得に興味があります。将来は、自身の研究内容や分野のみではなく、毒性全般に精通した研究者になりたいです。
自分の好きな漫画での「憧れてしまえば超えられない」という名言に感銘を受けて、座右の銘にしています。目標とする先輩を指標にして、先輩の考えや行動よりも一歩先を想像して行動に移すことで、自身を高められるように心掛けています。
毒性学の面白さ、並びに研究の楽しさを教えてくださいました、当研究室の中西 剛先生、松丸 大輔先生、石田 慶士先生に、心より感謝申し上げます。特に、私が研究室内で所属するチームで直接ご指導してくださっている石田先生には、研究に関する基礎知識から学会発表のコツなど、ここまで私を成長させてくださったことに感謝してもしきれません。今後ともよろしくお願いいたします!
ぜひ皆さんにも学会に参加してもらえたらなと思います。学会参加と聞くと、大変そうに感じるかもしれませんが、実験や準備が大変だった分以上に得られるものが本当に大きいです。私の場合、研究に関するアドバイスに加えて、アカデミアの先生方や企業の方とたくさん交流させてもらえました。観光も学会参加の醍醐味です!これからもお互い頑張っていきましょう!
所属
京都大学iPS細胞研究所
名前
横井 歩希
受賞タイトル
大腸オルガノイドを用いたIBDの病態再現および治療薬の評価
私はヒトES/iPS細胞から作製した大腸オルガノイドに炎症性腸疾患(IBD)の病態進行と関連するサイトカインを作用させ、IBDのサブタイプである潰瘍性大腸炎の病態の一部を再現することに成功しました。開発したIBDモデルを用いて既存薬の治療効果を評価し、本モデルは創薬研究にも応用できることを示しました。
ヒトES/iPS細胞を用いてヒト疾患モデルを作製しています。病態を忠実に再現した臨床予測性の高いモデルを毒性学および創薬研究に使用することで、新薬開発に必要なコストの削減や開発期間の短縮が可能になると期待されています。現在取り組むIBD研究ではヒトES/iPS細胞由来大腸オルガノイドを用いることで、腸管上皮細胞や間質細胞など生体大腸を構成する多様な細胞が炎症性サイトカインに応答し引き起こす病態を再現することができました。
炎症は体内へと侵入した異物や毒物を排除する働きであり、健康を維持するために重要な生体防御機構です。しかし、炎症が慢性化すると臓器を障害し、がんや動脈硬化、IBDなど深刻な病気に繋がります。万病の原因となる慢性炎症を完治する薬は人々の健康寿命を延ばすことができると考えられています。特にIBDは患者数が世界的に増加しているのにも関わらず根治療法がないことから、本研究を始めました。
本研究を始めた学部四年生の時は、実験操作に慣れるため比較的培養方法が簡単な癌由来細胞株に対するサイトカインの応答を調べていました。サイトカインに対する細胞応答は細胞種ごとに大きな違いはないだろうと考えていましたが、より生体大腸に似た細胞を使用し同じ実験を行うと癌由来細胞株とは異なる結果が得られたことに驚きました。本研究を通して、より生体に近いモデルを開発することの重要性を実感し、今後もそのようなモデルの開発に励みたいと思います。
ヒトES/iPS細胞から大腸オルガノイドを作製するときに、マトリゲル中で細胞が三次元的に大きくなっていく様子が面白いと感じました。ヒトES/iPS細胞から大腸オルガノイドへの分化誘導を毎回成功できるレベルの高い技術力を身に着けることが大変であり、現在も技術習得に励んでいます。
開発したIBDモデルを用いて、新規治療薬を開発することに興味を持っています。
「学びて思わざれば則ち罔し、思いて学ばざれば則ち殆し」(論語)
教わるばかりで自分で考えなければ本質を理解することができない、考えてばかりで他者から学ぼうとしなければ考えが凝り固まってしまい良くない、という意味です。
学部四年生の頃からご指導いただいています京都大学iPS細胞研究所の高山和雄先生にこの場をお借りして御礼申し上げます。
将来、本学会で皆さんの研究内容を知ることを楽しみにしています。
所属
東京大学大学院薬学系研究科 分子薬物動態学教室
名前
岩坂 拓海
受賞タイトル
メチレンジアニリンを用いた飲水肝機能障害モデルマウスの樹立及び毒性プロファイル評価
本研究では、メチレンジアニリンを用いて新規の飲水肝機能障害モデルマウスを樹立しました。本モデルは既存のチオアセトアミドを用いた飲水肝機能障害モデルと比較して、血液生化学値や肝病理像の時間変化が異なることが確認されました。また、投与初期の肝臓での遺伝子発現変化や免疫細胞の挙動についても違いが見られ、特に急性期では胆汁うっ滞様の肝障害を示すことが確認されました。本モデルは簡便に構築可能であり、かつ既存モデルと異なる毒性プロファイルを示すことから、肝毒性に関する様々な毒性学研究に有用であると期待されます。
一貫して肝機能障害の時間変化に着目して研究を行っています。
オミクスデータを用いた免疫細胞挙動推定をin vivoで再現していた際にDrug Induced Liver Injuryに興味を持ったのがきっかけです。
はじめはシンプルに化合物の投与に応じて異なる表現型が見られることが興味深く、種々の化合物を投与した際の表現型を調べたり、実際に実験したりしていました。現在は肝毒性の進展機序に不明点が多いことに興味を持っています。
データ解析で予見された現象がin vivo試験で確認できた際や、予想もしなかったような表現型が見られた際はとても面白かったです。一方で長期投与や経時変化の試験は体力的にかなり大変でした。(おかげさまで実験の技術は大きく向上しました。)
現在は個体の生死を分ける分岐点に興味を持ち、引き続き経時変化に着目しながら研究を行っています。将来の夢は特にありませんが、研究者をもっと世間の身近な存在にするための橋渡し的な存在になることができればと思っています。
“Is life worth living? It all depends on the liver.” (ウィリアム・ジェームズ)
いつも自由にやらせて頂きありがとうございます。引き続き精進いたします。
謙虚かつ楽観的に、これからもよろしくお願いします。
所属
東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学研究室
名前
三原 大輝
受賞タイトル
ニコチンはα7ニコチン性アセチルコリン受容体を介して肝臓線維化を増悪する
喫煙が肝臓線維化の深刻なリスクであることは過去の疫学研究から明らかにされていましたが、その具体的なメカニズムは不明でした。今回の研究で、肝臓におけるコラーゲン産生を担う肝星細胞において、活性型肝星細胞のみがニコチンの受容体であるα7ニコチン性アセチルコリン受容体を発現し、ニコチンによる本受容体の活性化がコラーゲン産生を促進することを明らかにしました。
α7ニコチン性アセチルコリン受容体が担う免疫制御機構や肝臓線維化を主に取り扱っております。その他にも、透析の一種である腹膜透析における合併症の発症メカニズム解析と、その予防・治療標的の探索、より良いモニタリングの手段を確立すべく、日々研究しています。
薬理学研究室に所属しており、日々様々な疾患の治療標的の探索を行っておりますが、現在行っている研究を社会実装していくという視点を持った際、毒性からの視点も必須であることを痛感し、そこから毒性の研究や勉強を始めました。
薬理と毒性は表裏一体であることを感じました。両方の知識を持ち合わせることで、より広い視野で生体現象を俯瞰できるようになったと感じています。知識量や研究技術は今後も向上させていく余地があると感じていますので、これからも精進していきたいと思います。
薬剤を投与し、様々な指標でその毒性を評価している際に、毒性がないことを言い切ることが難しいと感じております。0の証明は非常に難しく、実験設計・パラメータ設定を適切かつ最良に設けることは今後の私の課題だと考えています。そのためには、生体をより広く俯瞰する視点を養っていきたいと思います。
脂肪肝が非アルコール性脂肪性肝炎へと進行するきっかけは、実は明らかにされていないということもあり、そのメカニズムを解明することが現在の興味の一つとなっております。また、非アルコール性脂肪性肝炎に起因する線維化の抑止も興味があります。将来の夢は、多くの人に読んでもらえるような、インパクトのある論文を書くことです。
「人間の全盛期は常に未来にある」というチャップリンの言葉が好きです。去年より今年、今年より来年と常にレベルアップしていきたいです。個人的には、今年で30歳となり段々と体力の衰えを感じ始めておりますが、この言葉を胸に20年、30年走っていきたいと思います。
学部4年生から現在に至るまで、10年にわたりご指導いただいている堀正敏教授(東大獣医薬理)にこの場をお借りして感謝申し上げます。研究歴も浅い学部生のころから今に至るまで、私個人の考えや研究の進め方を一切否定することもなく、尊重して下さったことは、尊敬の念に堪えません。
研究生活には、心技体が欠かせないと考えております。日々の健康管理や、良い精神状況を保って、日々の研究に取り組んでいただければと思います。
所属
金沢大学 医薬保健研究域薬学系 薬物動態学研究室
名前
浅地 英
受賞タイトル
セロトニン動態/腸内細菌叢に起因した薬物性消化器毒性発現機構の解明
本研究では、薬物誘発性消化器毒性機構の解明を目的として、消化管内セロトニン動態および腸内細菌叢に及ぼす薬物の影響とそれに伴う水分挙動変動に関する詳細な検討を試みました。Caco-2細胞をはじめとするin vitro評価系を用いた取り込み試験、ラットin vivo/in situ実験ならびに次世代シーケンサーを用いたメタゲノム解析の結果から薬物性消化器毒性発現がトランスポーターを介したセロトニン輸送阻害に基づく管腔内セロトニンレベルの上昇とそれに伴う腸内細菌叢の変動に起因している可能性が示されました。
学部時代は、セロトニンの消化管動態について研究を行っていました。大学院進学後は、薬物性消化器毒性発現機構の解明に加えて、毒性発現の個体差変動の解明を目指しています。
研究室配属時に、テーマ説明で面白いと感じた消化管ホルモンのセロトニンに関する研究を選択しました。薬物によって消化管内のセロトニン動態の変動が生じることで消化器毒性が発現するのではないかと考え、毒性研究を始めたのがきっかけです。
研究を始めた当初は、毒性や腸内細菌叢についての知識は何もない状態だったので、新鮮な気持ちで取り組むことができました。毒性発現の複雑さに圧倒されていましたが、研究を進めていくことで機構が徐々に明らかになっていく過程に達成感を感じることができるため、それをモチベーションに日々奮闘しています。
消化管内には様々な生理環境を構成する規定因子が存在しています。薬物によって生じる消化器毒性について考察するうえで、多くの視点から複雑な考察をする必要があるため非常に大変であると考えています。
オルガノイドなどの消化管生理環境を模倣したin vitro評価系やPythonなどのプログラミングソフトを用いたデータ解析に興味を持っています。就職までに様々な実験手技や解析手法を習得し、幅広い分野で活躍できる創薬研究者になりたいと考えています。
「幸運は用意された心のみに宿る」ルイ・パスツール(フランスの細菌学者)
(時には息抜きも必要ですが)研究や勉強をサボってばかりいると、幸運を自分のものにできないと自身に戒める言葉としてとらえています。周りの人に恵まれてきたのも私自身が努力を続けてきたからなのかもしれないので、これからも継続していきたいと思っています。
研究室配属から現在に至るまでにご指導いただいている白坂善之先生にこの場を借りて感謝申し上げます。様々な学会発表の機会を与えてくださりありがとうございます。多くの貴重な経験をすることができ、様々な刺激を得ることができました。今後ともよろしくお願いいたします。
研究はうまくいかないことが多いと思います。それでも途中で投げ出さずに続けてほしいと思います。特に、毒性分野は考慮すべき要素が多いと感じているので様々な知識を身に着けることが重要だと思います。時には息抜きをしつつ頑張って取り組んでください。
所属
東京大学大学院薬学系研究科 分子薬物動態学教室
名前
橋本 芳樹
受賞タイトル
薬剤誘導性悪心・嘔吐のリスク評価に向けたヒト空腸幹細胞スフェロイドを用いたセロトニン放出評価系の構築
薬剤誘導性の悪心・嘔吐は消化器毒性の主要な症状でありながら、リスク評価に有用な評価系が枯渇しています。悪心・嘔吐の機序のひとつに、消化管の内分泌細胞からの過度なセロトニン分泌が嘔吐中枢を刺激することが挙げられます。受賞研究では、小腸スフェロイドを内分泌細胞へと分化させ、薬物刺激に伴うセロトニン分泌量を評価可能なin vitro実験系を構築し、セロトニン放出感受性と臨床における嘔吐発症頻度との対応性を評価しました。
当研究室では、医薬品の体内動態解析から小児肝臓難病の病態解明、バイオインフォマティクスに至るまで幅広い側面からトランスレーショナルリサーチを行っています。その中で私は、小腸スフェロイド/オルガノイドの創薬応用を目指しており、現在は薬剤誘導性の消化器毒性の包括的理解と定量的予測法の開発に努めています。
元々臨床に近い分野で研究をしたいと思い当研究室を志望しましたが、実験を進めるにつれ分子生物学的な基礎寄りの研究にも興味が出てきました。その点で毒性研究は、副作用のリスク予測の側面では臨床寄りの研究ができ、毒性機序の探索の側面では基礎寄りの研究ができ、両面の「いいとこどり」ができる分野だと思ったのでうってつけでした。本大会の年会長である北嶋聡先生が毒性学の面白さはその「網羅性」だとご挨拶で仰っておりました。私もまさにそのように感じています。
修士2年次より毒性研究を始め2年が過ぎましたが、当初は毒性研究のバックグラウンドもなく、また丁度指導教官がご栄転されたタイミングでもあったので、色々とお先真っ暗な中でのスタートでした。その中で、とりあえず気になったことはやってみようの精神でコツコツ実験を進めているうちに少しずつ自立して研究ができるようになり、学会で受賞できるまでに至れたのは非常に光栄に思います。
受賞研究に限った話となりますが、とある日、添付文書やインタビューフォームと睨めっこしていた際に、同種同効の医薬品でありながらも薬物の種類によって悪心・嘔吐の頻度がまるで異なる分子標的薬を見つけました。この薬物群の副作用リスクを絶対に再現したいと思ったのが、嘔吐のリスク評価系の構築に着手したきっかけです。セロトニン放出を評価可能な実験系をゼロから構築するのは大変でしたが、本研究で副作用リスクが再現できたときは本当に楽しかったです。
ハイスループットな毒性スクリーニング系の構築を行いたいと思っています。現状その段階には至れていないので、そのステージへ到達することが目標です。
「良い時こそ謙虚に。悪い時ほど明るく。」(山本由伸)と昨年度に書いて、あまり守れなかったので、戒めを込めて再掲します。
研究の面白さを教えてくれた指導教員の北里大学・前田和哉先生には感謝の言葉が尽きません。来年もこの文書を書けるように、頑張ります。
(当然、楠原先生にもいつも感謝していますよ!笑)
学会に参加するのは障壁が高いかもしれませんが、自分の研究を他者に知ってもらうことや、コミュニケーションを取り人脈を広げる経験は本当に楽しいです。私は学会を通じて、他大学の友達やアカデミアの先生方、企業のお知り合いの方を増やすことができました。そのような方々と再会できるのも毎回の学会の楽しみでもあります。もちろん観光やグルメもです。後輩の皆さんには、是非たくさんの学会に参加してこのような経験を味わってもらいたいです。
所属
協和キリン株式会社 トランスレーショナルリサーチユニット 安全性研究所
名前
弓桁 洋
受賞タイトル
In vivo target safety assessmentへの利用を目的とした迅速な後天的遺伝子欠損マウスの作製
医薬品の探索初期ではtarget safety assessment(TSA)を実施するためのツール化合物を用意できないことが多く、標的の検証はデータベース等を用いた調査に限定されることが多いです。現状コンディショナルノックアウト(cKO)マウスの作出は時間的要因からハードルが高いです。今回アデノ随伴ウイルスとゲノム編集技術を組み合わせることで、マウス生体において簡便かつ迅速に標的遺伝子を欠損できる技術を構築しました。
破骨細胞の分化機構について研究していました。破骨細胞は単核細胞同士の細胞融合により形成される骨を食べる性質を持つ非常に特異な細胞であり、そのダイナミックな分化機構に日々驚かされていました。
入社後に安全性研究所に配属されたことがきっかけです。大学の学部時代は獣医学を学んでいたこともあり、これまでの経験を最も発揮できる場所として安全性研究所への配属を希望しておりました。
始めた頃は認められた毒性の機序解明等、サイエンスを突き詰めることに特に楽しさを感じておりましたが、現在は毒性試験の結果を関係者と一緒に協議し、時には激しいコンフリクトも経験しながら、臨床開発が出来るように共に磨いていく、この一連のフローを通じた人とのコミュニケーションや折衝にこそ毒性研究の楽しさがあると感じています。
今回の発表テーマも一つですが、新規の毒性評価系を構築する業務はとてもやりがいを感じます。一方で、評価系を作る際には社内外におけるニーズや得られるリターンの度合い等も総合的に考える必要があり、本当に必要とされる評価系を考えることは非常に難しいと感じています。
評価・判断だけに留まらず、臨床での安全な使い方を提案し、新たな薬剤価値を創造できる安全性研究者になりたいと思っています。
子供のころ、外で捕まえた昆虫に「なんでわざわざこんな派手な模様で生まれてくるのか」と疑問を持つことがありました。大人になると、派手な見た目や奇妙な形態には必ず理由があることを知りました。研究を行う際には、「全ての現象には必ず理由がある」ことを意識しています。
大学の学部時代に研究の楽しさを教えて下さいました遠矢幸伸 教授には心から感謝しております。先生と研究終わりに、夜な夜な釣りに出掛けた日々は本当に楽しかったです。
自分なりの毒性研究の楽しさ、やりがいを見つけて下さい。困難な状況こそ成長につながるチャンスととらえ、チーム全員で立ち向かっていきましょう。
所属
東北大学大学院 薬学研究科 代謝制御薬学分野
名前
叶 心瑩
受賞タイトル
スルフォラファンによるNrf2非依存的なセレノプロテインP発現抑制機構
今回我々は、ブロッコリースプラウトの植物成分であるスルフォラファン(SFN)が、Nrf2非依存的な経路でリソソームの酸性化を促進し、主要なセレン輸送タンパク質であるセレノプロテインP(SeP)のリソソームでの分解を促進することを培養細胞からマウス個体レベルで明らかにしました。SePは糖尿病の増悪因子なので、将来的に治療薬シーズ開発に繋がる成果であると考えられます。
培養細胞や実験動物を用いて、有用植物成分によるSePの発現抑制のメカニズムについて研究しています。
当初、私は留学生で初めは有機水銀の毒性発現機構を研究するために来日しました。しかし、指導教員の斎藤教授からセレンの毒性・疾患リスクや有用性に関する研究を聞く中で、セレンの毒性と代謝制御機構に興味をもち、セレンに関する毒性学研究(毒性防御機構の研究ですが)をはじめました。
最初毒性研究は少し危険だと感じていましたが、今では毒性学は単純な毒性研究だけに限らず懐が広いことを認識しており、研究を通して関連する病気の予防や治療・安全性研究に貢献できることに価値を感じています。
実験して結果が予想と期待通りでないのは困りますが、偶然などから新しいメカニズムを発見するのが面白いと思っています。
セレノプロテインPについて、もっと研究を深めたいと考えています。
発見は、前もって積み重ねられた苦しい努力の結果です。――マリー・キュリー
私の研究が正しい方向に進むよう、いつも助けてくれてありがとうございます。
平常心で実験中の困難に立ち向かい、周囲に積極的に助けを求めることで、あなたの研究をより建設的かつスムーズにすることができるでしょう。
所属
徳島文理大学大学院薬学研究科
名前
田口 央基
受賞タイトル
フェロトーシスはシスプラチンによる近位尿細管S3領域の高感受性に関与する
我々は、マウス近位尿細管S1,S2,S3領域由来不死化細胞を用いることによってシスプラチンによる腎障害の解明に取り組んでいます。S3細胞はS1,S2細胞と比較してシスプラチンに高い感受性を示しましたが、その原因として細胞内におけるROS量、過酸化脂質量、遊離Fe2+量の増加などの複合的な要因によってフェロトーシスが誘導されていることが示唆されました。
学部生のころからシスプラチンによる腎障害機構に関する研究に取り組んできました。最近では、ヒ素化合物の発がんメカニズムに着目した研究にも取り組んでいます。シスプラチンとヒ素では共通性のない研究テーマではありますが、これまで学んだ知識や技術を応用することで現在研究を進めています。
多くのがん患者に使用されているシスプラチンが副作用として重篤な腎障害を引き起こしてしまうことを知り、薬の持つ毒としての側面に興味を持つようになりました。
研究を開始した当初は、知識も技術もなかったので、所属研究室の先生たちが実験をする姿を見て「なんか面白そうだから自分もやってみよう!」という考えでした。現在では、研究活動を通して少しずつ知識と技術も身についてきたことから自分の実験をどのように進めていくのか考えることが楽しいです。
実験で得られた結果を所属研究室の先生方と話し合い、次の実験に発展させることが楽しいです。大変なこととしては、地方私立薬学部では多くの学生が薬剤師になることを目標に入学していることから、研究にあまり興味のない学生が多いことです。少しでも研究に興味を持ってもらえるよう努力したいと考えています。
将来は薬学部の教員として、研究と教育活動に携わりたいと考えています。薬剤師が医療従事者として働く際に、研究活動で培った問題に対して臆さず立ち向かう力や解決するために自ら考える力は非常に重要になってくると考えています。このような能力を学部生の研究活動を通して身につけられるように指導ができる教育者になりたいです。
所属研究室の角大悟先生、藤代瞳先生、前教授である姫野誠一郎先生には日々の研究活動において支えていただいております。先生方の学生目線に立って、最後まで見捨てることなく教育を続ける姿勢を尊敬しています。
指導教員である角大悟教授にこの場をお借りして感謝申し上げます。大学院に進学しようと考えたのは、先生と共に研究を続けたいと強く感じたからです。先生の温かいご指導のおかげで、とても幸せな大学院生活を送ることができています。今後ともご迷惑をかけることも多々あるとは思いますが、ご指導よろしくお願いいたします。
研究室の後輩たちは、常に明るく前向きな人たちでいつも元気をもらっています。あなたたちのおかげで日々楽しく研究活動を行えています。この場をお借りして感謝申し上げます。これからもみんなで飲みに行きましょう。
所属
東北大学大学院薬学研究科衛生化学分野
名前
鈴木 若奈
受賞タイトル
ポリペプチド系抗菌薬による腎機能障害発症の新たなメカニズムの解明
環状ポリペプチド系抗菌薬であるコリスチンは優れた殺菌作用を持ち、多剤耐性グラム陰性桿菌に対する最終救済薬として注目されています。しかし頻発する重篤な腎機能障害が問題となっており、コリスチンによる腎機能障害発症メカニズムの解明が求められています。本研究では、コリスチンは近位尿細管細胞においてマクロファージの浸潤促進因子を誘導する作用と、腎に浸潤したマクロファージのNLRP3インフラマソームを活性化し、炎症反応を誘導するという二つの作用により、強く腎機能障害を惹起することを明らかにしました。
細胞内のシグナル伝達機構に注目し、生体が薬剤や活性酸素といったストレスに対するストレス応答として、炎症や細胞死を誘導する際の詳細な機構について解析を行っています。
細胞内ストレス応答機構についての研究を行っている研究室への配属がきっかけです。
研究室に配属される前には、「毒性」というと環境汚染物質のような「毒」のイメージが強いものを思い浮かべており、それらが人に与える悪影響や、疾患がもたらされる機構について解析を行っているという印象を持っていました。現在では、それだけではなく、治療のために使用される薬剤が副作用としてもたらす毒性の機序解明など、幅広いテーマを含んでいることを知り、その奥深さに興味を持っています。
細胞内で起こっている特定の現象について分子機構を詰めていく過程で、予想とは反する結果が出た時は、面白くもあり、大変でもあると感じます。結果を説明するための仮説を、文献を調べながら再考することは大変な作業ではありますが、実際に起こっている生命現象に一歩近づいたような感覚は研究の醍醐味であると思います。
細胞死に興味があります。特に近年では新しい誘導機構・形態の細胞死が報告されているので、その生理的意義や病理的な側面、既知の細胞死との関連を含め、詳細が明らかになってくると面白いと考えています。
座右の銘はないのですが、私を支えているのは両親や兄妹といった家族の存在です。研究者の道を志すことができたのは、両親の理解と助けがあったからです。自分が希望するままに好きな道に進ませてくれたこと、応援し支え続けてくれていることに対して、いつか恩を返せたらと思います。
日頃から親身にご指導くださる、東北大学大学院・薬学研究科・衛生化学分野の松沢厚先生、野口拓也先生、平田祐介先生に、心より感謝を申し上げます。特に私が所属する研究室内のグループで直接ご指導をいただいている野口先生には、研究の進め方からプレゼンテーションのコツまで、右も左も分からなかった自分を育ててくださったことに、深く感謝を申し上げます。
何をするにしても、健康第一です。適度に周囲とのコミュニケーションを取り、大変な時には誰かを頼って、一緒に頑張りましょう。皆様がそれぞれの分野でご活躍されることを願っております。
所属
東京大学大学院薬学系研究科 分子薬物動態学教室
名前
東 一織
受賞タイトル
大規模毒性データベース利活用に向けたdeconvolution法の検討
Deconvolutionは、トランスクリプトームデータより試料中の免疫細胞比率を推定する機械学習手法です。本研究では、組織特異性や動物種差を考慮したモデリングが免疫応答の精緻な推定に重要であることを見出しました。同手法を大規模毒性データベースに適用することで、免疫応答に関する集約的な知見が取得可能となり、毒性発現機序の理解が進展すると期待されます。
臨床情報やオミクスデータなどヘテロで高次元な特性を有するデータに対して、潜在変数モデルを構築することで、試料を特徴づける解釈性の高い生物学的情報の抽出に取り組んでいます。
オミクス情報を利用した免疫応答推定モデルの解析対象として、薬物性肝障害に興味を持ったことがきっかけです。
現在まで一貫して、毒性発現の動物種差やヒトへの外挿性を考慮した解析手法の確立を重視しており、困難な一面もありますが、同時にやりがいを感じています。
解析対象に応じ、適切なモデリングを論理的に構築する過程が面白いです。提案モデルの妥当性を生物学的に評価する際には、多くの実験を実施する必要があり大変でした。
医療薬学の現場で実際に求められる手法と、数理情報学的なアプローチで実現可能な手法とを橋渡しできるような研究者を目指しています。
ストイックであれ。
ストイックな姿勢を見習いたいと思います。今後ともよろしくお願いします。
奥深い毒性研究に一緒に取り組んでいきましょう!